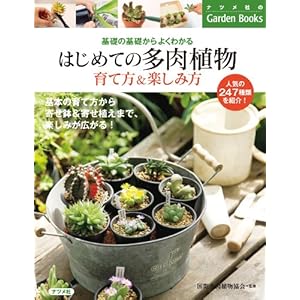Café WALKABOUTは趣味の部屋です。
自由なくつろいだ空間にしたいですね。
特にジャンルを決めることなく、日常のできごとなどを綴っていこうと思います。ポレポレやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
【アフェリエイト広告を利用しています】
| まな板 |
| 2025/12/12 |
|
ポリエチレン(PE)製のまな板は抗菌性など衛生面が高く、また安価なので汚れたら買い換えると言う考えで使っていたのですが、今年の7月から木製のまな板に替えて使っています。 実家の木製のまな板で包丁を使うと心地良く切れるので、我が家でもそうしようと思ったのです。勿論、実家の包丁の砥ぎが良いのもありますが、木製のまな板だと包丁の当たりがPEとは異なり柔らかな感じがするのです。 衛生面に関しては、使用後は必ず洗って乾燥させればそれほど問題ないと思いました。 実家にあるようなずっしりしたまな板は高価なので、まずはお試しにお手頃価格のヒノキのまな板を買ってみました。スタンダードな大きさ(40cm×22cm)で厚さ1.5cmのものです。届いた時はヒノキの良い香りがしましたが、使っている間にすぐに香りはしなくなりました。重さは思っていたよりも軽かったです。まな板は同じ大きさでも材質によって重さが違います。樹の繊維が緻密であるほど重く、実家のまな板はそのようなものだったのですね。調べてみるとまな板に最適な樹はイチョウなのだそうで、おそらく実家のまな板はイチョウだと思います。 ヒノキのまな板を使って半年が過ぎますが、使ってみて感じたのは包丁の刃の持ちがPEより良いように思います。材質がPEよりも柔らかいため、刃こぼれしにくいのですね。PE板の時は3ヶ月もすると包丁の切れ味が鈍くなってきたのですが、木製板は6ヶ月後でも、少々切れ味は落ちているものの、まだ砥がなくても良いくらいなので違いは明らかです。これほど違うとは思っていませんでした。 独身時代にも木製まな板を使っていた頃があったのですが、PE板を使うようになってからはずっと替えずにいたので違いが分からなかったのです。 PE板は安価で取扱が簡単(食洗器も使える)なので手軽さと安心感がありますね。一方、木製板は包丁を入れた感覚がとても良く、刃こぼれしにくいのですが、使用後は常に洗って乾かし衛生面に気を付ける必要があります。どちらも一長一短ありますが、今の私は木製のまな板の方を使いたいですね。 そのヒノキのまな板ですが、値段が安かったこともあると思いますが、角がささくれてきました。それで家にあるカンナ(鉋)で削ることにしました。ついでに表面も軽く削って整えてみました。傷を全て削り取ったのではありませんが、状態が良くなったように思います。 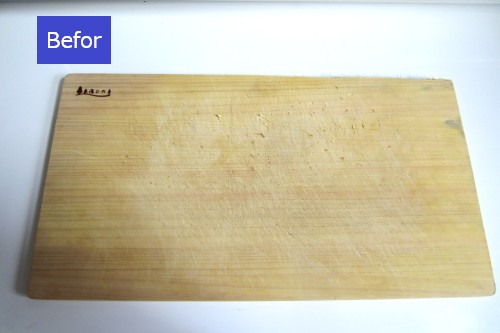
 
 最後に、つい先日「イチョウのまな板」を買ってしまいました。歳末セールで半額になっていたので、ついポチっとしてしまいました(笑)。小ぶり(30cm×20cm)で厚さ2.5cmのものです。先のまな板をメンテナンスしたので、これはまだ使っていないのですが、使い始めは特別な日にしたいなと思っています。  |
| 【PR】 |
| 風味香るエビのソテー |
| 2025/12/5 |
|
師走に入り、今年も残り少なくなってきました。師走だからと言う訳ではないのですが、ここのところ休日は何かと家族の予定が入っていて、記事にするようなことが無く、今週の更新はどうしようかと思っていました。 このサイトの運営方針は自分のペースで行うと言うのが大前提にあるのですが、それでも週1回ここに記事を載せたいという思いもあります。 SNSとは違い、見て頂いた方の反応(いいねなど)を感じることはないのですが、それでもたまにサイトのアクセス統計を見ると訪問してくれている方がいるのが分かり、嬉しい気持ちになります。それが、次の記事を載せようと思うモチベーションになっているのは確かですね。記事の内容は個人的な他愛ないものですが、それでも見てくれている方がいらっしゃると言うのは本当に嬉しいです。 しかし、SNSなどの双方向で繋がる環境に身を置きたいとは思っていません。フォロワー数や反応数に捕らわれたくないからです。例えるなら、親しい友人がたまに家に遊びに来てくれて一緒に会話や食事などを楽しむような、そんな感じで運営していきたいと思っています。 さて、仕事帰りに寄ったスーパーでエビ(ブラックタイガー)が安くなっていたので買って帰りました。記事にするために買って帰ったのではないですが、どう料理しようかと考えていたところ、久しくやっていなかった簡単で美味しい調理方法を思い出し、それを記事にしてみようと考えたのです。何も特別な物ではない、でも特別な感じが得られる料理です。クリスマス料理の1品として出しても良いかもしれませんね。(私個人の思いです(笑)) 風味香るエビのソテー(エビソース和え)(※私が勝手に命名してます(笑))  材料 材料・エビ(殻付き)12匹 ※出来れば有頭 ・ニンニク1片(チューブでも可) ・オリーブオイル(サラダオイルでも可) ・小麦粉適量 ・白ワイン200ml(日本酒でも可) ・塩、コショウ少々 ・ハチミツ小さじ1杯(メイプルシロップでも可) ・タイムやバジル、パセリなどお好みの香草少々(無くても可) A(エビの汚れ落とし) ・塩小さじ1杯 ・酒少々 ・片栗粉少々 【エビの下準備】 (1)エビの殻をむく(むいた殻は残しておく) (2)むきエビの背に包丁を入れて背ワタを取り除く ※背ワタに未消化のエサなどが残っていると臭みや食感が悪くなります ※出荷前に絶食させて背ワタに異物が残らない処理をしているものもあります (3)(2)をボールに入れAを加えて軽く混ぜ混む (4)(3)を水で流し洗いザルに取る(汚れがきれいに取れます) (5)キッチンペーパーで(4)の水分を拭き取る 【エビソース作り】 (1)フライパンにオリーブオイルを大さじ2杯程度入れる (2)むいた殻を(1)に入れ、弱火でじっくり炒っていく (3)殻が赤から白っぽくなってきたらフライパンの端に寄せる (4)フライパンの空いた場所に少量のオイル入れ、そこにニンニクのみじん切りを入れて炒める(弱火のまま) (5)ニンニクの良い香りが立ってきたら殻と混ぜ合わせ、白ワインを入れる (6)ヘラで殻を押さえるようにして混ぜ殻のエキスを出す (7)塩少々とハチミツ小さじ1杯を加え煮詰める (8)煮詰める間に味見をして塩気や甘味が足りないようなら塩やハチミツを加える (9)完成したエビソースを器に取る。その時、殻を押さえて汁を出してやる ※エビの頭があるとエビミソが加わりさらに濃厚なソースになります ※エビの頭を入れた時は、しっかり中まで火を通すと生臭さがなくなります ※頭を炒る間はヘラなどで押さえず、ワインを入れてから押さえるとエビミソが焦げずに美味しいエキスが取り出せます 
 
 【エビのソテー】 (1)下準備したエビに軽く塩・コショウし、小麦粉を入れたビニール袋に入れ、袋を振ってエビに小麦粉を付ける (2)フライパンにオリーブオイル大さじ1杯を入れ、火を点けてオイルを温める (3)オイルから湯気が立ってきたらエビをフライパンに入れソテーする(オイルが足らないようなら適量追加する) (4)エビが色付いてきたら返して反対側も同じようにソテーする。 (5)反対側も色付いてきたら、エビソースを加えて絡める。 (6)エビにソースがしっかり絡んだら完成 お好みで香草を散らす 
 今回は無頭エビを使いましたが、有頭エビであれば風味もコクも濃厚になって美味しいです。 そうとは言え、無頭でもエビの香りが出ていて美味しかったです。 香草は収穫したタイムを振りました。 是非、試してみてください。  |
【PR】  |
| マジョラム |
| 2025/11/28 |
|
夏から秋にかけて花を咲かせる植物が気温の低下で弱ってきたので、植え替えしたいという妻と一緒に、久しぶりに園芸ショップに行ってきました。 妻は耐寒性のあるビオラやチューリップの球根を選んでいましたが、その間、ショップのタイムサービスが偶然開催されたので、私はそそくさとそちらを覗きに行きました。移動可能な大きなパレットが2台あって、その棚に売れ残った感のある植物のポットや、苗木、鉢植えのバラなどが置かれていました。どれも半額になっていて気に入ったものがあればお買い得です。 その中でフィオリーナというビオラのポット苗があったのでそれを1つ買うことにしました。フィオリーナは昨年の冬に鉢植えしていて、寒い季節でも可愛い花を良く咲かせてくれたのでとても印象が良いのです。 それからチコリやコリアンダーなどのハーブのポットも置いてあり、そこに「スイート マジョラム」があることに気付きました。マジョラムは良い香りのするハーブで、トマト料理などに合います。近頃、良く行くスーパーには置いておらずあまり気に留めていなかった(タイムやオレガノでも代用できるので)のですが、苗木を見つけたことで自宅に植えてみようと思ったのです。 マジョラムは乾燥を好むことから、同じような条件を好むタイムを植えている横に植えてみることにしました。マジョラムはやや寒さに弱いので、気温が下がってきているこの季節での植え付けはあまり適しているとは言えないのですが、値段が安かったこともあり、ダメもとで植えてみることにしました。どうなるか分かりませんが無事に冬を越せることを願っています。 鉢植えにして寒い間は室内で育てた方が確実なのですが、当初から地植えを考えていたのでそうしませんでした。根付いてくれると嬉しいですね。  |
| 【PR】 |
| 乾燥タイム | ||
| 2025/11/21 | ||
|
植えているタイムの枝が伸びているのでカットすることにしました。 タイムは低木性のシソ科の植物で種類が多いのですが、我が家に植えているのはコモンタイムでハーブとして料理などに使えるものです。 コモンタイムは立性で枝を上に伸ばすのですが、その枝どうしがぐちゃぐちゃ絡まってこんもりした樹形になります。タイムは比較的乾燥した気候を好み(ヨーロッパ南部が原産でそこは乾燥した地中海性気候ですね)、風通しが悪いと蒸れて枝葉が枯れることもあるので、枝が混んできたらカットして通気性を良くしてあげるのです。勿論、カットした枝に付いた葉は料理やハーブティーに使えます。   今回は沢山刈り込んだので、取れた枝葉を乾燥させて「乾燥タイム」を作ることにしました。枝葉のまま干しますが、使うのは葉だけです。「乾燥タイム」はスーパーなどの香辛料売場などでも売っていて、葉のものと粉末にしたものがありますね。 ハーブの本やハーブに関するおしゃれなサイトの写真などでは、ハーブを束にしてぶら下げて乾燥させていますね。私も初めはそうしたのですが、束にすることで通気性が悪くなり乾燥しにくいと考え、干し網に移し広げて乾燥させることにしました。見た目はおしゃれではありませんが、乾燥させると言う目的からすると合理的ですよね(笑)。日光に当てて乾燥させると香りが飛んでしまうそうなので室内で干すことにしました。晴れの日が続いていたこともあり、3日目にはほぼほぼ乾燥していました。  枝と葉を分別する作業をします。枝に小さな葉が付いているのですが、いらない紙(新聞紙など)を敷き、その上で枝を指でしごくようにして葉を紙の上に落としていきます。乾燥しているので、比較的簡単に葉は外れます。先端部など一部外れにくいものもありますが、そのばあいは指先で摘まみ取ります。初めは丁寧に作業を行っていたのですが、量があったので、そこまで丁寧にする必要性は無いと感じ、外れにくい物は無視することにしました。 その作業が終わったら、次は収穫した葉の山に混ざった小枝を取り除きます。目視の他に、葉を親指と人差指で少量掴み、指の間でこすりつけるようにすると取りやすくなりました。葉の部分が外れて、硬い枝が指の中に残るのです。そうとは言え、ざっと適当にやって終わりです。 最後に獲れた乾燥タイムの葉を保存瓶に入れます。使ったのは、市販の粉末タイムの入れてあった香辛料の空瓶と、マスタードが入っていた空瓶です。丁度この2つの瓶に全量が入りました。 私は比較的頻繁にタイムを使っています。我が家にタイムを植えたのもそれが理由です。タイムは鶏や魚料理にとても合いますね。鶏や魚の臭みが消え、嫌味のない爽やかな風味があります。またトマトの煮込み料理などにも合います。 それからラムチョップにもとても良く合いますよ。今では値段が高くてなかなか買えないのですが、塩、ブラックペッパーにタイム、オレガノ、バジルをまぶしてフライパンで焼くと最高に美味しいのです。オーブンで焼くよりも、フライパンで焼く方が簡単で、旨味たっぷりの脂が落ち過ぎないのも良いですね。表面を強火で焼いてから、蓋をして蒸し焼きにし、概ね火が通ったところで蓋を外し、もう一度強火で表面を焼きつけると美味しくできます。肝心なのは火を通し過ぎないことですね。中が少し赤っぽいぐらいの方が美味しいです。レア気味の方が肉質が柔らかくて食感も良く、旨味も多いです。火の通し具合がこの料理の肝ですね。 お好みですが、私は最後にレモン汁を振りかけるのが好きです。フライパンの中で肉にレモンソースをまんべんなく絡ませて出来上がりです。レモンの酸味がラムの脂っぽさを軽減し、ソースにはしっかりと香草の香りが含まれていて実に美味しいのです。簡単に出来るのでキャンプで作っても良いですね。個人的には牛肉のステーキよりも好きです。 この料理には何と言ってもタイムは欠かせないです。羊肉独特の匂いが苦手な方もいると思いますが、タイムがその匂いを和らげてくれ、肉が滋味深く感じられるのです。タイムのあるなしでかなり違うので、もし気になる方はお試しください。タイムの効果が分かると思います。 タイムは本当に使い易くて便利なハーブなので、使ったことが無い方は、是非試しに使ってみてください。美味しさがアップグレードすること間違いなしです(ちょっと言いすぎかも…)。  |
||
【PR】
|
| 双眼鏡 | ||
| 2025/11/14 | ||
|
秋が深まってきました。 鳥の囀りにひかれてバルコニーに出てみると、電信柱の頂上にモズの姿がありました。 庭にもシジュウカラが帰ってきました。サクランボの樹にいる芋虫などを食べているようですが、もう少し寒くなったら給餌台を用意してあげなきゃと思い始めています。 秋冬はバーディングに良い季節ですね。肉眼で鳥を探すのも楽しいですが、遠くにいる個体を見るには双眼鏡などの光学機器があるとより一層楽しくなります。 鳥の撮影を趣味にしている方々はバズーカ砲のような超望遠レンズを持っているのを結構見掛けますね。そのような方々も双眼鏡はたいがい持っています。視野角の狭い望遠レンズでは鳥を探すのが難しいからですね。 ご存知だとは思いますが、双眼鏡にはおもに 「ガリレオ式 」「 ポロプリズム式 」「 ダハプリズム式 」 の3つのタイプがあり、鳥や動物の観察には「 ポロプリズム式 」「 ダハプリズム式 」が良いですね。「ガリレオ式」は軽いのですが構造上倍率を上げるのが難しい(4倍程度)からです。また、倍率や視野角、防水性などの違いがありますが、8倍~12倍で視野角の広いもの(30°以上)が鳥や動物の観察に適しています。動きの速い物は視野角が広い方が追いかけやすいのですが、視野角が広くなるほど対物レンズが大きくなるので携帯性は悪くなります。因みに私が持っているコンパクトタイプの物は10×22と10×25です。そのくらいでも動きが早くなければ探すのに困ったりすることはあまりないです。防水性は必要とまでは言えませんが、やはりあった方が良いですね。雨に濡れなくても、急激な気温の変化によってレンズ内に曇りや水滴が発生することがあるからです。長く使うつもりなら防水性があると安心ですね。 私は「ポロプリズム」「ダハプリズム」式の両方の双眼鏡を持っていますが、個人的には「ダハ」の方が好きですね。鏡筒がまっすぐなので小さいものはコンパクトに畳めてポケットに入ります。気軽に持ち運べるのが良いです。  その双眼鏡などの光学機器ですが、ネットショップなどでついつい見てしまうのです。双眼鏡やカメラレンズなどの光学機器は複数持っているのに欲しくなってくるのですね。カメラを趣味にしている方は「レンズ沼」などと呼んでいますね。 私に関しても、ネットショップを何気なく見ていたはずなのに、いつのまにか真剣に比較検討していて気付いたら1時間を超えていたなんてことが少なからずあります。カートに入れた後で思い留まることも多々あり、かろうじて「沼」に足を踏み入れずに留まっています(笑)。 光学機器は高額な物は性能が良いですが、低価格であっても思いのほか良い物があったりします。双眼鏡は結構当たりが多いように思います。ちょっとした時に使う程度であれば、リーズナブルな価格の物であれば買っても良いなって思いますよね。 半年前のことですが、ついつい今までもっていなかった単眼鏡を買ってしまいました。光学性能は普通でしたが、値段がとても安かったのでコストパフォーマンスは良いと思います。しかし、あまり必要ない物なのですけどね… 双眼鏡は強い衝撃を受けたりしない限り壊れることは少ないように思いますが、15年以上前に買ったNikonのリーズナブルな価格の双眼鏡が、10年経過した頃に鏡胴を包むプラスチック(ポリウレタン)が加水分解してベタベタになり一部は欠けてしまいました。加水分解は湿気が多いと起こるのですが、一緒に保管していた他の双眼鏡はそのようなことはありませんでした。一流メーカーであるNikonの品質管理上、素材の選定に関しどうなのかなと思ってしまいました。そうとは言え、光学系には全く問題がないので、プラスチック部分を取り除き、べたつきをエタノールで拭き取って今も使っています。中央のプラスチックカバーも取り外せるのですが、構えた時にカバーがある方が手にしっくりくるので付けたままにしています。  |
||
【PR】
|
| 干物日和 | ||
| 2025/11/7 | ||
|
休日にカマスと小アジ、小イワシが手頃な値段で売っていたので買って帰りました。その日は朝から青空が広がる秋晴れで風もあり、干物を干すのに丁度良い天気でした。 カマスは8匹、小アジと小イワシは皿盛で2皿ずつ買ったのですが、数えてみるとそれぞれ32匹と30匹でした。どれも下処理されていたので内臓などのゴミが出ないのが嬉しいですね。アジとイワシは小さいのでそのまま丸干しにすることにしました。 塩水に1時間ほど漬けてから、干網に魚を並べ、風通しの良い場所に吊るします。干網は3段あるのですが、久しぶりに全ての段を使いました。夕方に場所をバルコニーに移してそのまま朝まで干しました。ほぼ1日(約22時間)干しましたが、良い具合に干せました。  
 
 さっそく焼いて食べてみました。カマス1匹、アジとイワシはそれぞれ2匹です。 カマスは干すと旨味が増して本当に美味しいですね。個人的にはそのまま塩焼きにするよりもこちらの方が好きです。塩焼きのふわふわした食感も良いですが、やはり旨味は干した方が出てきますね。 アジとイワシは小さいのでそのまま食べてみました。アジはイワシよりも骨が硬いのですが、問題なく食べられました。ただ、今回食べたものよりも大き目のものがあったので、それは頭からガブリは難しいかもしれません。イワシは頭を取っているのでさらに食べやすかったです。背骨も全く気にならないぐらいでした。 そして、アジにはアジの、イワシにはイワシの固有の美味しさが感じられました。アジの独特の風味は刺身でも塩焼きでも干物でも感じられますね。イワシは小さいながら脂を蓄えた肉質で噛むと口の中に脂の旨味が拡がります。これは酒の肴に持ってこいの味ですね。そのままでも、マヨネーズ(七味唐辛子を加えて)をディップして食べるのも良いです(小アジにも合います)。 アジとイワシは同じ青魚ですが全く異なる味で、例えるならアジは山手育ち、イワシは下町育ちと言った感じではないでしょうか? こんな例えで分かりますかね?(笑) 久しぶりに沢山干物を干したのですが、食べやすさもあり、すぐに消費してしまうかもしれませんね(主に酒の肴で)。 日本酒を買ってこようかな…  |
||
【PR】
|
| サンマの一夜干し |
| 2025/10/31 |
|
今年はサンマやイワシ、イカが豊漁とのニュースがありましたが、どれも店頭価格はそれほど安くなっていないと感じますね。人件費や輸送代など全てが値上がりしているので、それを加味すると販売価格が「安くなった」と実感できるほどではなくなるのかもしれません。大衆魚と呼べるのはもうイワシぐらいかもしれませんね。 遅い時間にスーパーに行ったところ、たまたまサンマが半額になって売っていました。1匹125円ぐらいになっていました。今年はサンマはあまり食べていないので買って帰ることにしました。冷蔵庫には肉類の在庫があったことと、下の子は好んで魚を食べないので、日持ちする上に食べやすくなる一夜干しにすることにしました。 頭と内臓が取られていたので腹開きにしたのですが、1匹目は綺麗に開けたのですが、包丁の刃に脂が残っていたためか2匹目は柔らかい腹が少し引き千切れてしまいました。脂が多いと切った後は毎回包丁を洗って刃先を綺麗にしないとそうなってしまいます。でも味は変わらないので良しとします(笑)。 天候があまり良くなかったので冷蔵庫内で干すことにしました。バットに水分を拭き取ったサンマを並べて庫内で1日半乾燥させました。良い感じに出来ましたよ。 魚グリルで焼いて食べましたが、やはりサンマは美味しいですね。干すことによって肉に程よい弾力(硬さ)が加わり、塩焼きと違った食感を楽しめます。下の子も一応食べてくれました。 秋らしく気温が下がってきましたね。これからの季節は干物作りに最適です。 先日、小イワシを干したのですが、焼くと骨まで食べられ美味しかったですよ。 「さあ、これから何を干そうか」と楽しみです。  |
| 【PR】 |
| 飛行機 |
| 2025/10/24 |
|
久しぶりに飛行機の窓側席に座りました。マイレージ特典航空券や格安航空券で窓側席を取るのはなかなか難しいのですが、今回は時期が良かったのかたまたま取れてしまいました。 海外便など長時間乗る場合はトイレに行くなど便利な通路側の席が良いのですが、国内線など短時間であれば窓側の席も良いですね。離陸や着陸時、飛行時に見える景色を眺めるのが好きなんです(笑)。私は子供の頃から「乗り物」の中で飛行機が一番好きでした。たぶん自由に空を飛ぶイメージから好きになったのだと思います。 往路の出発時は曇っていたこともあって、普段通りに寝入ってしまいました。しばらくして起きると、窓の外には雲は多いもののその切れ目から山々が見えていました。寝ていたこともあり位置は定かではないのですが、たぶん南アルプスの山麓ではないかと思います。山肌の斜面の約半分が茶褐色に色付いていて、そこは紅葉しているのだと思います。 その後進むに連れて雲の様相が変わってきました。いつしか空一杯に「イワシ雲」が広がっていました。イワシ雲を見上げることはありますが、眼下に見るので何だか嬉しい気分になりました。そして、そのまま外の景色を見続けていると前方からすうっと滑るようにJAL機が通り過ぎて行ったのです。まるでそこに見えない軌道があるかのように一直線に飛んで行ったのです。窓側の席に座ると時々このような光景に出くわすので楽しいですね。出会いは3秒ほどなので写真に撮ることはなかなか出来ませんね(笑)。 
 大分空港の上空は晴れていて、窓からはっきりと空港が見えました。一度大きく旋回して着陸体制に入りました。高度が落ちてくると窓から海面が見え、そこに機体の影が映っているのが分かりました。本当に久しぶりに窓の外ばかり眺めていたなって思います(笑)。 
 復路では「鳴門大橋」が見えました。写真を撮ったのですが、機体のほぼ真下だったので隅っこにあるのが分かるでしょうか? 他機のすれ違う姿を撮りたいとコンパクトカメラを出して待っていたのですが、その機会はありませんでした。でも、空の青さと大陸のように広がる白い雲は心を捉えて離しませんでした。吸い込まれそうなブルーは雲の近くの明るいブルーからグラデーションして上空に行くほど濃く深いブルーになっています。この青の美しさは心の奥深くまで浸透するようで、その青を見ていると自分の心が穏やかに浄化されていくような不思議な気持ちになっていくのが感じられるのです。  話は変わりますが、ポケモンジェットを見つけるとついつい写真を撮ってしまいます。子供が小さい頃はポケモンジェットを見つけるととても喜ぶので写真に撮っていたのですが、今ではそれほど興味はないようです。そうとは言え、今でも私はポケモンジェットを見つけるとついつい撮ってしまいます。 今回見られたのはAir Doのロコンジェットとソラシドエアーのナッシージェットです。因みにANA機はピカチュウジェットとイーブイジェットがあって国際線に就航しているようですね。 
 |
【PR】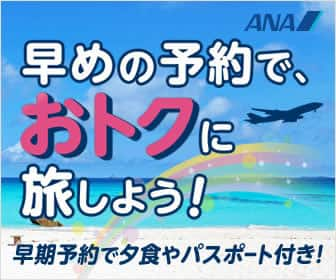 |
| 足湯(別府市鉄輪) |
| 2025/10/17 |
|
大分県別府市は温泉で有名ですね。古くからの湯治場の面影を残す鉄輪(かんなわ)では豊富な温泉の湧出があり、道を歩いていると側溝から湯気が上がっているのが見られます。 また入浴料が100円の公衆浴場が幾つもあるのですが、料金は入口に設置された賽銭箱のような箱に入れるだけで誰でも入れます。そうとは言え、公衆浴場の入浴を目的にしていないと観光や散策の途中でお風呂に入ることはあまりないと思います(宿泊する旅館やホテルにも大概温泉がありますからね)。 散策中にふらりと立ち寄るのに最適なのが「足湯」ですね。バッグにタオル1枚入れていれば気軽に利用できます。温かい湯に足を浸けてゆっくりとした時間を過ごすのも悪くありません。たまに読書している人も見かけました。グループでも一人でも楽しめるのが良いですね。 別府は火山活動によって形成された扇状地で山側から海に向かって坂が続いています。鉄輪の地形もそうで、冒頭に記した温泉水が側溝を勢いよく流れているのもそのためです。 さて、足湯の話に戻りますが、私が行ったところを簡単に紹介しようと思います。 鉄輪には「いで湯坂」と言うメイン通りがあります。この通りをさらに上ると「みゆき坂」になり、この通りは「別府地獄めぐり」で有名な「海地獄」「鬼石坊主地獄」「かまど地獄」「鬼山地獄」「白池地獄」のあるエリアに続いています。みゆき坂には新旧のお土産屋さんや飲食店がならび、温泉の蒸気で蒸した地獄プリンなども売っています。しかしこの通りには足湯はありません。 それではここから「いで湯坂」を下っていくとしましょう。通りを少し下って右側に「地獄蒸し工房」があります。ここでは好みの食材を選び温泉の蒸気で蒸し料理を作って食べられる施設です。私はここで食べたことはないのですが、いつも賑わっていて人気があるようですね。その蒸し工房の先に「足湯・足蒸し湯」があります。木造の建物ですが、入ってみると奥には壁がなく、屋根の有る露天風呂のような風情がします。足湯は細長い溝の両側に腰掛けるようになっており、20人ぐらい座れると思います。湯が出るところには竹製の「湯雨竹(ゆめたけ)」と呼ばれる冷却装置に湯を通して足湯に湯を供給していました。上流ほどお湯は温かいのですが、私が入った時は上流でも丁度良い温かさ(40℃ぐらい)でした。 「足蒸し湯」の方はやっていませんでした。ながらく休止しているように思います。 ここは通りに面しているので結構来る人が多く、外国人の姿も見受けられました。そうとは言え、混雑した感じはなくのんびり過ごせました。    「いで湯坂」をさらに下っていくと永福寺と言うお寺があり、その先に「渋の湯」と言う公衆浴場があります。そこの路地を少し左に入ったところに「むし湯」があります。ここは一遍上人が創設した名湯で「草湯」と言う薬草を敷いた部屋で温泉の蒸気を使ったサウナのような風呂(?)もあります。 この「むし湯」の入り口手前に「足蒸し湯」がありました。勿論無料です。「足蒸し湯」と言うのは温泉の蒸気で足を温めるもので足だけのサウナと言う感じです。こちらは蒸気が足に当たるので結構熱かったです。体感的に足湯よりも足の疲労回復に即効性があるような気がします。こちらは定員5人です。私がお昼前に行った時は誰もいませんでしたが、午後4時頃に行ってみると地元のお婆さん5人が足を入れて談笑していました。もしかしたら健康の秘訣として足蒸し湯を利用しているのかもしれませんね。 
  いで湯坂には2つの足湯(足蒸し湯)がありましたが、最後にもう1つ穴場的な足湯を見つけました。 いで湯坂の終点からさらにどんどん下っていくと「大分香の博物館」があります。そこの裏庭に小さな足湯があったのです。小さな庭ですが、樹や花、青空を眺めながら開放的な空間で足湯に浸かるのは本当に気持ちが良かったです。特に館内に案内はなく、裏庭に出てみないと足湯があることが分からないので、殆どの来館者は気付かずに帰っているような気がします。 そんな博物館の足湯に浸かっていると、ふと毬栗に気付きました。栗の木が近くにあって落ちていたのを誰かが拾って置いたのかもしれません。九州はまだまだ暑かったですが、秋はやってきているのですね。 
  余談ですが大分空港のロビーにも足湯がありました。大分空港は現在サンリオとコラボしていて期間限定(2026年3月末まで)で大分ハローキティ空港となっています。そのため足湯の「のれん」もキティちゃんとシナモロールになっていました。  【参考】 〇別府鉄輪温泉湯けむり散歩 - inakade-ho |
| 【PR】 |
| サワラとブリの一夜干し |
| 2025/10/9 |
|
ようやく秋らしくなってきましたね。日中でも日差しが柔らかくなったように感じます。 スーパーでサワラ(鰆)の切り身が売られているのを見つけました。大き目の切り身で見るからに美味しそうなので買って帰りました。 サワラは淡泊な白身でクセがなくとても美味しい魚ですね。塩焼きやムニエル、フライなどにしても良いですね。私は味噌漬けにして焼くことが多いです。味噌漬けにすると日持ちもする上、身の水分が丁度良く抜け、味噌の旨味も加わってとても美味しいからです。西京漬けのようなものですね。白みそでなくても美味しくできますよ。 今回はサワラを一夜干しにしてみることにしました。サワラは干したことはなかったのでちょっと楽しみです。 切り身を塩水に漬けますが、麺つゆを少し加えました。淡泊な味なので少し旨味成分を加えた方が良いと思ったからです。冷蔵庫で1時間半ぐらいおいてから取り出し、表面の水分をキッチンペーパーで取り、干し網に並べて干しました。 サワラは水分量が多く、干したのが夜中だったのと身が厚かったので、朝に触ってみてもまだ干し足らない感じでした。それで日陰に網を移動させてしばらく干しました。その後気温が上がってきたので、サワラを取り込んで冷蔵庫に入れてさらに干しました。身を触ると指に吸いつき弾力がある感じになったら完成です。 夕食にサワラの一夜干しを焼いて食べてみました。とても上品な味で実に美味しかったです。お酒に良く合いますね(笑)。  それからブリの切り身も一夜干しにしてみました。こちらもサワラの漬け汁と同じ割合にしました。 ブリの一夜干しはあまり聞いたことが無かったのですが、ネットで調べてみるとすぐにヒットしました。スーパーなどの店頭では見ることはないので意外でしたね。 ブリはサワラに比べて水分量が少なく、また切身も小さめだったので冷蔵庫で半日干したら良い具合に乾きました。 焼いてみると、身が程よく締まっているのですがパサつきはなく、麺つゆの効果なのか、噛むと旨味が感じられ想像していた以上に美味しかったです。こちらも酒の肴になりますね(笑)。 サワラとブリの新たな楽しみ方を見つけました。  |
【PR】 |
| 蛍光灯型LED |
| 2025/10/3 |
キッチン天井のベースライトの蛍光灯が切れてしまいました。 2027年末から蛍光灯の製造・輸出入が禁止になることがTVなどで告知されていますが、LEDに替えるか蛍光灯のままもう少し引き延ばすか決めかねていました。 我が家のキッチンベースライトはグロースターターを使って蛍光灯を点灯するもので、この形式であれば工事無しで蛍光灯型LEDに替えられることが分かっていました。しかし安定器が古いと熱を持ち、最悪の場合発火する危険性があるとの情報もありLEDへの交換を躊躇していたのです。 しかし実際問題、電灯が消えてしまっているので早急に対応しないと不便だったこと、時間が経過するほどに安定器の劣化が進むことを考えると、早めにLEDに替えた方が良いように思えてきました。それでLEDに変更することにしました。 蛍光灯型LEDランプが届き、グロースターターを取り外した状態でランプを取り付けました。スイッチを入れると点灯し、異音がしたりチラついたりなど、特に異常は見られなかったので安心しました。このまま様子をみていこうと思います。 蛍光灯を点灯するには安定器が必要ですが、LEDランプの点灯には安定器は不要です。その安定器や器具(ソケットや端子台など)の劣化が事故の原因となるのが分かりました。なのでLED交換が事故を引き起こす訳ではなかったのです。LED交換が事故発生の原因と誤解を生むような表記の仕方が多く、メーカーやリフォーム会社の意図的な誘導が感じられます。正確な情報を提供して欲しいと思いますね。 そうとは言え、器具を取り付けて15年以上経っている家は多く、劣化による事故発生の恐れはぬぐい切れないことを考えると、工事(安定器を外す、またはバイパスする。新たにLED器具を取り付ける)した方が安心なのは確かですね。 また安定器を外さずLEDに交換した場合は、安定器が電気を消費するため、省エネ効果は薄れます。そのようなことを考えるとLED器具に交換・工事するのが一番よさそうですね。 【参考】 蛍光灯器具をLED化する際はまるごと照明器具交換を推奨します | LED照明ナビ | JLMA 一般社団法人日本照明工業会 |
| 【PR】 |
| サバの味醂干し |
| 2025/9/26 |
|
朝晩はようやく秋らしく涼しくなってきましたね。 昼間はまだ高温になりますが、夕方からは涼しくなるので久しぶりに干物を作ろうと思いました。 スーパーの鮮魚コーナーに行ってみると、小ぶりのマサバが手頃な値段で売っていたので買ってきました。今回はひと手間かけて味醂干しにしてみました。 サバを軽く水洗いして血合を取り除きます。その後キッチンペーパーで水気を取って軽く塩を降り10分ほど置きます。普段干物を作るときには塩水に漬けるのですが、味醂醤油につけるのでそうしました。塩を振ると身から水分が出てつけ汁が染み込み易くなるからです。ここでも浸透圧の原理が出てきますね。 サバの表面に出た水分を拭き取って、つけ汁に浸します。つけ汁は味醂と醤油を100mlづつ、お酒を少し(30mlぐらい)を合わせました。どれも目分量なので正確ではありません(笑)。 そしてサバを漬けたタッパーごと冷蔵庫に約3時間程度置きます。その後、つけ汁から身を取り出して表面の水分をキッチンペーパーでざっと拭き取り白ゴマを振りました。その身を干し網に並べ、バルコニーで一晩干してみました。朝になり身を触ってみると、まだ半乾きの状態だったので、冷蔵庫内で乾燥させることにしました。日中は30℃ぐらいになる予報だったからです。 出来上がってさっそく焼いてみると香ばしい香りがしました。しかし食べてみるとあまり脂がありませんでした。今年は暑かったのでたぶんサバの脂付きも遅いのだと思います。脂ののった秋サバはとても美味しいので心待ちにしています。見るからにはじけそうなぐらいにパンパンに張った身の旬のサバの美味しさは最高ですよね。  |
| 【PR】 |
| サボテン | ||
| 2025/9/19 | ||
| フシギダネの鉢を作った時に多肉植物を植えてみたのですが、それ以来、多肉植物に興味が出てきました。特にサボテンはその形が可愛いので鉢を増やすことにしました。サボテンや鉢は100円ショップで売っていたものを購入しました。そして土は前回使ったハイドロボールを使ってみることにしました。 サボテンの育て方を調べてみると、土はサボテン用の土が売られていて初心者はそれを使うのが一番良さそうでした。しかし敢えてハイドロボールを使ってみることにしました。またハイドロボールは底穴の無い鉢で使用するのが一般的なのですが、穴のある鉢に入れて使ってみます。ハイドロボールは素焼きの粒なので水はけが良すぎる心配がありますが、乾燥地の植物であるサボテンであれば、給水をコントロールすれば育てられると思ったからです。また肥料は含まれていないので、定期的に肥液を与えることで対応することにしました。そうとは言え、サボテンはあまり肥料を与えなくても良いようです。 買ってきたサボテンを苗ポットから取り出し土を優しく落としていきます。土が根に絡まって落とし難いですが、根元を水に浸けて振るようにして落としていきます。植え替えてから新しい根が出るはずなので、根元以外の根は切れてもあまり気にしませんでした。土を落としたサボテンはそのまま日陰で乾燥させました。根が濡れていると根腐れの危険性があるようだからです。個人的な考えですが、乾燥させることで植物の生育状態をリセットさせる意味合いもあるのだと思います。その刺激により新たな根が出やすくなるような気がします。  根が乾いたら小さめの鉢にハイドロボールを入れてサボテンを植えました。鉢はサボテンの大きさに合わせて選ぶと良いそうです、大きすぎる鉢だと土が保水して根腐れし易くなるそうです。ハイドロボールはあまり保水しないようですが、本来のハイドロカルチャーでの使用方法(穴の無い鉢で育てる)だと、底に水が溜まるので、注意が必要ですね。 実際、前に瓶に植えたサボテン(マミラリア)は、水を与えすぎたようで根腐れしてしまいました(涙)。それを教訓にサボテンの栽培に再チャレンジです。 私のやり方(ハイドロボールを穴あき鉢で使う)で上手く育てられるか分かりませんが、何事もトライですね(笑)。   |
||
【PR】
|
| ラズベリーと桑の実のお酒 |
| 2025/9/12 |
|
6月初めに仕込んだラズベリーと桑の実のお酒が飲み頃になりました。 ラズベリー酒は初めて作りましたが、綺麗な紅色で、ラズベリーの香りと甘酸っぱい味が感じられ美味しかったです。ラズベリーをそのままお酒にしたと言う感じです。 桑の実はそのまま食べると香りや甘さが少なくぼやけた味なのですが、果実酒にすると香りが引き立ちます。また、果実のエキスを抽出するために入れた氷砂糖の甘さも相まって、甘さの中に桑の実独特のコクが感じられます。桑の実はジャムや果実酒に加工した方が美味しく食べられますね。  その桑の実酒ですが、1年前に作ったものと飲み比べてみることにしました。 まず色味なのですが、今年の物は深い赤紫色(ガーネット色)ですが、1年前の物は赤紫色にわずかに薄茶色を纏った感じでした。ぱっと見では違いが分かりませんが、少量をグラスに取って光を透かせてみると色の違いが分かります。 口に含んでみると、今年のは桑の実の香りと味がストレートに感じます。1年物については、香りは桑の実なのですが、色と同様に味はまろやかに変化していました。味はほんのりとワインのような風味がします。大げさに言うと、貴腐ワインのような香りと味を感じました。飲む前はそれほど違いはないだろうと思っていたので、その変化に驚きました。何故か、オーストラリアのアデレード郊外にあるペンフォールズ醸造所で飲んだ15年物のワインの味を思い出しました。  
 以前の記事「お酒の熟成」で「お酒は液中成分の化学反応で熟成が進む」と記載しましたが、新・旧の桑の実酒を飲んだ結果、実を取出して3ヶ月以降も熟成が進んでいたことは間違いないことが分かりました。好みによりますが、桑の実らしいフレッシュな香りと味を楽しみたいのであれば若いお酒を、熟成したお酒が飲みたいのであれば1年保管してみるのも悪くはないと思います。 これまでに自家製果実酒に関するサイトやブログなど見ていますが、新物と1年経過した物との味を具体的に比較した記事には出会っていませんでした。なので、今回の結果は期待しておらず、ちょっとしたサプライズになりました。 「ウィスキーは瓶詰後は熟成が進まない」のは原液自体が無味無臭のエチルアルコールに加水したもので、熟成樽の成分が溶け出て初めて熟成が進むからであり、樽から出せば添加物の供給がストップするので熟成は止まるということですね。 自家製の果実酒もその原理で考えていたのですが、果実成分は私が思っていた以上に化学変化が継続するようです。 調べてみると、ワインでは瓶詰後に保管熟成させる方法もあるようなので、それと似たような反応なのかもしれません。 因みに、「発酵」と「熟成」の違いですが、「発酵」は酵母などの微生物が糖類を分解してアルコールを生成することで、「熟成」は溶液に含まれる有機酸、ポリフェノール、タンニンなどの成分が化学変化することで風味が増すことです。 ※製造免許を持つ者を除き、「発酵」によるアルコール生成は原則として酒税法上禁止されています。 【参考】 〇日本蒸留酒酒造組合 ご自宅で、果実酒(果実のお酒)を作る場合のご注意 |
| 【PR】 |
| 残暑 |
| 2025/9/5 |
|
9月になり夕暮れが少し早くなったと感じますが、猛暑日が続くので、庭作業など外での活動はなかなかできないでいます。 ネットニュースに子供の夏休みの宿題の「アサガオの観察」で、高気温のため「花が咲かない」「種ができない」「枯れた」などがあったと掲載されていました。 我が子の時もそうでしたが、小学生のアサガオ観察は、学校で育てていたアサガオの鉢を自宅に持って帰り、それを観察するというものでした。学校で光合成を学び、光を当て成長を促す意図で日向に鉢を置いた児童も多いと思いますが、今年の夏の想像以上の照射熱に(鉢植えであるが故の水分供給不足も加わって)耐えられなくなってしまったケースが多いのではないかと推測されます。 また日陰であっても、鉢に挿した予備の500mlのペットボトルでの給水では足らず、家族旅行から帰ってきたら枯れていたなんてこともあるかもしれませんね。それほど今年の夏は気温が高いのだと思います。 実は我が家でも同じようなことが起きていて、高温と強い日照により、1日水を与えるのを忘れてしまったことで、イチゴが枯れてしまいました。 イチゴは前日まで濃い緑の葉で新しい茎を伸ばしていたのですが、たった1日で干からびて茶色に変色していました。その後、水を与えてみましたが回復することはなく、完全に枯れていました。 他の鉢植えに関しては、影響があったものとあまりなかったものがあります。寄せ植えしていた鉢は枯れてはいないもののひどく弱ってしまいました。回復は難しいかもしれません。 サクラモコモコは暑さに強い耐性があるようで、元気一杯に花を咲かせています。1日ぐらいの給水忘れでは大丈夫そうですね。そうとは言え、去年の夏に旅行から帰ってきたら弱っていたので、この猛暑下ではせいぜい3日が限度だと思います。旅行など出かける場合は、日陰に鉢を移動させてたっぷり給水してから出かけると暑さの影響は軽減されると思います。 ミョウガのプランターは半日陰になるところに置いていたので大丈夫そうです。それでも、葉が薄茶色に変色した部分があり、影響は出ていますね。 地植えの植物にも影響が出ていて、ブルーベリーの葉の一部が黄色くなっていたり、ラズベリーは葉が枯れてしまった茎があったりします。ラズベリーは実を付け始めているのでもっと頻繁に給水した方が良いのですが、裏庭にあることもあり、ついつい忘れがちになっています(涙)。 昨今、夏には天気予報などで「命に関わる危険な暑さ」と言う言葉が頻繁に聞かれ、その際にはエアコンの効いた屋内で過ごすことが推奨されています。熱中症警戒アラートが頻繁に出され、公園に子供の姿がない景色なんて、私が子供の頃には考えられませんでした。これまでの常識が通用しない、ニューノーマルの時代になっているのだなと感じます。否が応でも環境について考えさせられますね。 「色鮮やかな夏の思い出」 取り戻したいですね。  |
| 【PR】 |
| ミニチュアフィギュア | ||
| 2025/8/29 | ||
子供が幼い頃に行った水族館で、色々な種類のカエルのミニチュアが入ったセットを買いました。子供が選んで買ったのですがそれはかなり良く出来ていて、遠目でみると本物っぽく見えました。子供は成長とともにカエルからポケモンに興味が移り、一部なくなってしまった物もありますが、今ではカエルは私のデスクに並んでいます(笑)。 さて、ガチャガチャやガチャポンと呼ばれているカプセルトイがありますね。今では色々な場所に販売機が設置されていて、多くの人が楽しんでいる姿があります。 そのカプセルトイですが様々な物が入っていて驚かされます。何百、何千種類もあるのではないかと思わされますね。 その中には生物のミニチュアフィギュアが入っているものがあり、その出来栄えに驚くことがあります。そのような物を見ると、大人の私でもついつい欲しくなってしまいます。 少し前になるのですが、そんなミニチュアがネットショップでも売られているのを知り、「ネイチャーテクニカラー日本の清流 増補特装版」と「ネイチャーテクニカラー日本のカメ 特装版」を勢いに任せて購入しました(笑)。    届いたミニチュアフィギュアは造形や体色がとても良く表現されていて、子供の玩具とは言えないぐらいでした。生物好きな人はきっと欲しくなると思います。 メーカーの「株式会社いきもん」のWebページを見てみると、自然科学や芸術をモチーフに玩具を製作するトイメーカーとのことで、「上質なネイチャートイを世界中に拡げることで未来の研究者や芸術家たちの気づきのチャンスを増やしたいと考えています。子供たちの手の届くところに上質で知的な玩具を届けること、おもちゃの力で世界の未来を豊かにすることが目標です。」と記載されていました。また、トイの製作においても専門家の監修を受ける等、本気度が伝わってきます。「子供騙し」ではない「子供のための玩具」は大人も魅了しますね。 メーカーの公式ネットショップを見ると、購入したものは既に完売しているようです。それ以外にも、気になるものは軒並み完売していました。オークションなどでも出されているようですが、アイテムにより定価の3倍・4倍もするものもあるのでびっくりしました。有る時に買っておいて良かったなと思っています。 新しく加わったミニチュアは100円ショップで買ったケースに入れて私のデスクに置いています。何だか、嬉しい気分になりますね。  |
||
【PR】
|
| 自家製ジン(その2) |
| 2025/8/22 |
|
前回作った自家製ジンはジュニパーベリーよりもカルダモンとフェンネルの香りと味が強く、アクアビットのようになってしまいました。 その経験を踏まえ、今回はジュニパーベリーとタイムを入れたウォッカと、カルダモン、フェンネル、ローズマリーとローレル(月桂樹の葉)を入れたウォッカの2種類を用意し、2週間後に合わせてみることにしました。 ジュニパーベリーとタイムを入れたのは、個人的にタイムの香りが好きなのと、タイムは比較的香りが薄いのでそうしました。1週間後と2週間後に香りを嗅ぐと、ジュニパーベリーの香りが増していてジンらしくなっていました。 もう一方の瓶は候補のボタニカルを別けて漬けても良かったのですが、面倒なので一緒に入れてみました。また今回はミントの代わりにローレルを入れてみました。 こちらは1日経過して香りを嗅いでみると、カルダモンの香りが強くしていました。他の材料と香りや味がアンバランスにならないように1日目でカルダモンを取出しました。そして1週間後、2週間後に香りを嗅いでみるとカルダモンの香りが弱まりマイルドになったような感じがしました。 余談ですが、カルダモンの香りはコカ・コーラにも感じるような気がしました。コーラのレシピは公開されていませんが、たぶんカルダモンが入っていると思います。  2週間が経ち、2つを合わせてみました。ジンらしくジュニパーベリーの松のような芳香と優しい苦味をはっきり残したいので4:1の割合で混ぜてみました。試飲してみるとジンらしい香りと味になりました。メインはジュニパーベリーの香りですが、その中に爽やかなカルダモンと青草のようなフェンネルの香りがします。またカルダモン由来の辛味とフェンネル由来の苦味も感じられました。タイムとローズマリー、ローレルに関しては、微妙に香りを感じますが、知らなければ気付かない程度でした。入れなくても良いかもしれませんが、自家製に拘るのであれば、やはり自家栽培のハーブを入れたいですよね(笑)。 これを冷たい炭酸水で割って飲むと口の中に芳香が広がり、なかなか美味しかったです。レモンの皮(レモンピール)を加えるともっと美味しくなりそうです。 今回の結果から、ボタニカルの素材の特性を知ったうえでスピリッツに漬ける時間を調整した方が良いことが分かりました。中でもカルダモンの香りは強く、漬ける時間は半日ぐらいでも良かったかもしれませんね。 ジンはジュニパーベリーの風味がメインであること以外に決まりごとはありません。コリアンダーやキャラウェイなどの香辛料やお茶の葉などを入れたものもありますね。身近な素材としてシソ(紫蘇)を入れてみても良いかもしれません。 因みにジュニパーベリーだけのものも飲んでみましたが、シンプルな風味はそれはそれで美味しかったです。 備忘録として今回の作り方を残しておきます。 ①ジンのベース酒 〇ウォッカ700ml 〇ジュニパーベリー 30粒 〇タイム枝 30本(15㎝ぐらい) ②添加用ボタニカル酒 〇ウォッカ 400ml 〇カルダモン 1粒(1日経って取り除く) 〇フェンネル 15粒 〇ローリエ 1枚 〇ローズマリー 5本(15㎝ぐらい) 2週間後、①400mlと②100mlをブレンド(4:1の割合)する。 ボタニカルに使う素材は限定されていないので、自由な発想でオリジナルのジンを作るのも楽しいですね。  ※訂正 前々回記事で作ったお酒はアクアビットみたいなものになっていたのですが「ジュニパーベリーを入れているのでジンと言えるかもしれません」と記していました。しかし確認してみると、ジンの定義はジュニパーベリーの風味が主体となっていることが必要だと分かり、前回作ったものはジンとは言えないことが分かりました。ここで訂正します。 |
| 【PR】 |
| 深宇宙展 |
| 2025/8/15 |
|
日本科学未来館(東京お台場)で特別展として催されている「深宇宙展」に行ってきました。 会場に入ると、プロローグとして当企画展の趣旨や展示の説明映像を見てから展示エリアに足を踏み入れます。 まず最初にあったのは日本のH3ロケットの先端部の実物大模型でした。その先はロケットの部品や日本のロケット開発の歴史が分かる展示内容でした。国産第1号ロケットとなるペンシルロケットなどの展示もありました。このエリアは「ロケットが導く宇宙」と言うコンセプトでロケット開発が宇宙開発の礎であることが分かります。  次に人口衛星の縮小レプリカや部品などの展示があり、さらに進むとソユーズの帰還モジュールが展示されていました。このモジュールは実際に使用されたもので、前澤有作氏がISS(国際宇宙ステーション)に行った時に使われたソユーズロケットに搭載されていたものです。 次に人口衛星の縮小レプリカや部品などの展示があり、さらに進むとソユーズの帰還モジュールが展示されていました。このモジュールは実際に使用されたもので、前澤有作氏がISS(国際宇宙ステーション)に行った時に使われたソユーズロケットに搭載されていたものです。モジュールの表面を見ると、大気圏突入時に空気が圧縮されて生じた高温の熱のために黒っぽく変色しているのが見て取れました。モジュールの傍にスロープが設けられていて、そこを昇るとモジュールの出入り口から内部が見られました。定員は3名ですが、その狭さに驚きました。殆ど身動きできないのではないかと思われるほどです。しかし、その臨場感から宇宙を少しだけ身近に感じられたように思います。モジュールの横には宇宙服の展示もありました。前澤氏が着ていたものです。  次のエリアはアルテミス計画に関する展示でした。ご存じの方が多いと思いますが、アルテミス計画とは有人の月面探査の計画です。日本人クルーも2名が予定されています。 まず、大きな月面探査ローバー(車)に圧倒されてしまいます。銀色の6輪車で、SF映画に出てきそうな車体が格好良いです。TOYOTAのロゴが付されていました。 また月探査のための機械装置の展示などもあり興味深いです。トランスフォーマーの玩具メーカーで知られるタカラトミーも協力して開発された小型探査ロボットLEV-2(SORA-Q)の展示もありました。 余談ですが、アメリカのトランプ大統領の方針からNASAの予算削減や人員整理などが当計画に影響しないか心配しています。各国が協力する国際的な計画なので、順調に進むことを心から願っています。   その先には巨大な赤い大地が大画面に映し出されていました。NASAの火星探査機から送られてきた画像データを合成して作られた映像です。この迫力ある映像は必見です。疑似体験とは言え、火星の姿を間近で見ている感覚がします。この映像から火星にも確かに大気があることが感じられました。因みに火星の大気の主成分は二酸化炭素だと分かっています。 その他に、火星やその衛星の探査計画や開発している機器のレプリカなどが展示されていました。 最後のエリアは太陽系やその先の宇宙(太陽系外宇宙)に関する展示でした。 そこには探査機「はやぶさ」が小惑星イトカワから採取した粒子と、「はやぶさ2」がリュウグウから採取した粒子を顕微鏡で観察できました。私は粒子を見たからと言って何か触発されることはなかったのですが、子供たちがこれをきっかけに宇宙や科学に関心を持てたら良いなと思います。実際、多くの子供(大人も含め)がそれを見るために順番待ちで並んでいましたね。 そして最後の展示は、すばる望遠鏡やアルマ望遠鏡などの観測データから分かってきた宇宙の姿や地球外生物の可能性など、まだまだ謎の多い宇宙についての映像が大画面に映し出されました。その中に地球外生物の映像(想像図)があったのですが、それは以前NHKスペシャルで放映された映像と同じものでした。この展示の主催者としてNHKの名があったので納得しました。 特別展の会場を出てから、最上階(7F)にあるレストランで昼食を取りました。オムライスを食べましたが美味しかったですよ。それから、レストランからお台場のガンダム像も見えました。 食事の後は、5Fと3Fの常設展示ゾーンを見ました。その頃には来館者が増えて混雑しており、並ばずに済むものをざっと見て回りました。それから言い忘れていましたが、館内に入ると最初に気付くのが、巨大な地球儀ジオ・コスモスです。人工衛星から撮られた地球の画像データ3ヶ月分を地球儀表面に映し出しているそうです。雲の流れる様子や、大陸の形が分かるので面白いですね。楽しみながら地理の学習が出来そうです。 宇宙や地球を知ることで、子供たちが大きな視点で物事を見て考えられるようになれたらと思っています。(大人もですが…) 【参考】 〇特別展「深宇宙展〜人類はどこへ向かうのか」To the Moon And Beyond 〇日本科学未来館 (Miraikan)  |
| 【PR】 |
| 自家製ジン | ||||
| 2025/8/8 | ||||
|
暑い季節になると、ジンを飲むことが増えてきます。爽やかな風味なのが良いですね。 氷を入れたグラスにジンと炭酸水を入れて飲むのが好きですね。炭酸水が無い時は水で割っても良いです。その際、レモン汁を少し入れると美味しいですよ。 ジンはジントニックやジンリッキー、マティーニなどのカクテルベースにもなるお酒ですが、別に難しいことを考えずにそのまま飲んだり、ジュースで割って自分好みのカクテルを作ってみるのも良いですね。自分好みのオリジナルカクテルが見つかると、それも嬉しいですよ。飲み方なんて自由で良いのです。 近頃は巷でジンが流行っているようですね。ジンに参入するメーカーがとても増えてきているように思います。洋酒メーカーのみならず日本酒や焼酎のメーカーのジンも販売されていますね。私がジンを飲み始めた頃は販売されていた銘柄は少なかったのですが、今は地方の酒蔵が作ったクラフトジンなどもあり、本当に多くありますね。 ジンは蒸留酒(スピリッツ)に植物由来のものを入れて風味付けしたお酒です。市販品の多くは風味付けした後に再蒸留しボトリングしたものなので透明です。 ジンを作る上で欠かせないのがジュニパーベリー(セイヨウネズの実)です。この実を入れないことにはジンと名乗ることはできません。この実がジン独特の香りと味のベースを作るからですね。そこに色々なハーブや香辛料などを加えるのですが、それらは全て植物由来のものであることからボタニカルと呼ばれています。そのボタニカルの種類や配合、抽出方法などの違いが、メーカー各社のジンの違いを生み出しているのですね。 そのジンですが、自分で作れるのを知り試しにやってみることにしました。スピリッツとジュニパーベリーに好みのハーブや香辛料を入れれば出来ます。再蒸留しないジンはバスタブジンと呼ばれるそうです。19世紀のイギリスやアメリカ合衆国の禁酒法があった時代に、バスタブで(隠れて)作っていたことがその由来だそうです。 ジン作りにあたり、ベースにするスピリッツはウォッカにしました。初めて作るので、なるべく無味無臭に近いものが良いと思ったのです。スピリッツに入れるボタニカルがお酒にどのような風味を与えるのか興味があったからです。 ボタニカルについては、ジュニパーベリーとカルダモン、フェンネルを購入しました。それに庭にあるローズマリー、タイム、ミントを軽く乾燥させて入れてみることにしました。自家製なので、やはり自宅にあるものも使いたかったのです。市販のジンに比べると6種類で少ないですが、どのようになるのか全く分からないので最初としてはこのくらいで良いのかなと思いました。   さて、作り方ですが上記のボタニカルを適当にウォッカの瓶に入れるだけです。 初めて作るので、適正量など分からず、本当に適当に入れてみました。 〇ウォッカ 700ml 〇ジュニパーベリー 18粒 〇カルダモン 3粒 〇フェンネル 小さじ1 〇ローズマリー 1本(15㎝ほど) 〇タイム 10本(15㎝ほど) 〇ミント 3本(15㎝ほど)   2週間経って試飲することにしました。 まず瓶のキャップを開けると、カルダモンの香りが強く感じられました。爽やかな匂いの中にスパイシーさがある独特の香りです。 お酒の色は透明だったものが、透明感のある褐色に色付いていました。 まず、ストレートで味わってみました。お酒を口に含むと、強いカルダモンの香りが一杯に広がりました。次にほろ苦さとピリッとした辛味が感じられ、その中に青草っぽい香りも感じます。薬用酒と言う感じでした。青臭さと苦味はフェンネルから出ているものだと思います。ローズマリーとタイム、ミントについては感じられませんでした。カルダモンとフェンネルの量が多かったのだと思います。 炭酸水で割って飲んでみると、爽やかな香りとほろ苦さが以前飲んだことのある味に似ていると気付きました。記憶を呼び戻しながら飲んでいると「アクアビット」の味だと気付きました。 アクアビットは北欧の蒸留酒で、ずっと昔(20代後半頃)に酒屋さんで見つけて興味本位で買って飲んでみたお酒です。当時は薬草臭くてあまり美味しいと感じませんでした。その時に感じた香りとほろ苦さが思い出されたのです。 今回作ったお酒はジュニパーベリーを入れているので一応ジンと言えると思いますが、ジュニパーベリーの香りや味はあまり感じられず、むしろアクアビットに近いものになってしまいました。 初めからボタニカルの配合を一発で決めるのは無理だったようですね。分かったのはウォッカ700mlに対しカルダモンとフェンネルの量が多すぎたと言うことですね。 自分好みの配合を見つけ出すのはまだ先のようです(笑)。次はまずジュニパーベリーだけで漬けて基本の原液を作り、そこに他の材料を入れていくやり方でやってみたいと思います。 このアクアビットのようなジンですが、私の味覚の幅(苦みの耐性含め)が拡がったこともあると思いますが、冷たい炭酸水で割って飲むとさっぱりとした爽快感と嫌味のない苦味で意外といけるのです。暑い夏に合いますね。気が付いたら1日でボトル半分ほど飲んでしまったのですが、薬効があるのか、次の日も頭スッキリで二日酔いになりませんでした。(だからと言って飲みすぎはダメですね(笑)) お気に入りの自家製ジンへの道のりはまだまだ続きそうです。  ※掲載の写真を撮影後、漬けていたボタニカルは取り出しました。 |
||||
【PR】
|
| 焼かない粘土 | ||||
| 2025/8/1 | ||||
|
「ひなたぼっこ」と言う商品名の焼かない粘土で小さい鉢を作ってみました。 興味を覚えて3月にこの商品を買ったのですが、そのままになっていてようやく開封したのです。 4ヶ月以上も置いておいたので、中身が乾燥して使い物にならないのではないかと心配しましたが、少し硬くなっているものの手で練ることができたので使えそうでした。 しかし練ってもすぐにぽろぽろになってしまうので、全体を水に浸けてから取り出し、ビニール袋に入れ密閉して1日置くことにしました。 翌日確認してみると、少しべたつくものの、加工できるぐらいの柔らかさになったので、鉢作りに取り組んでみました。 鉢になる部分は、ラップを巻いた瓶に板状にした粘土を巻き付けて型取りしました。この時、瓶底よりも粘土板を少しはみ出させます。そのはみ出た部分を内側に折りたたむようにして瓶底を覆い鉢底を作りました。 これで鉢は出来ましたが、それだけではつまらないので、装飾を付けることにしました。参考にしたのは子供が好きなポケモンです。鉢に観葉植物でも入れようと考えていたので、フシギダネのような形にしてみることにしました。 鉢は胴体部分になるので、頭と足を残していた粘土で作成します。それを木工用ボンドで胴体に接着して作業完了となりました。 そこから自然乾燥させるのですが、時間の経過とともにあちこちみ亀裂が現れてきました。調べてみると、表面や内側、厚みの違いなどから粘土の乾燥する速度の違いからひび割れが生じることが分かりました。特に夏は気温が高いためひび割れしやすいようです。既に表面が硬化してきていたので、そのまま乾燥させることにしました。 ひび割れしないようにするには、乾燥の速度を均一にすることが求められることが分かりました。気温が高い時期などは、軽く濡らした日本手ぬぐいに包んで乾燥させると良いような気がします。それからもっと小さな、例えばペンダントサイズの物であればひび割れは出にくいかもしれませんね。 乾燥させたフシギダネの表面にはあちこちひび割れが出来ていましたが、鉢は割れていないので使えそうです。意外に割れた部分が爬虫類系の皮膚っぽく見えるのも面白そうです。フシギダネは幼少のポケモンなので皮膚はツルっとしていそうですけどね(笑)。 それでも少しは見栄え良くするため、フシギダネ鉢を軽くサンドペーパーで磨きました。頭部のひび割れはそれほど深くなかったので、つるりとした表面になったのですが、胴体である鉢部分のひび割れは深く、サンドペーパーで磨いても滑らかになりそうになかったので、軽く磨いて終わりにしました。 最後の仕上げにアクリルガッシュで塗装しました。塗装すればひび割れも目立たなくなると思ったからです。 実はアクリル絵具とガッシュは同じような物と思い、色むらが出にくいガッシュを買ったのですが、よくよく調べてみるとアクリル絵具の方が耐水性が高いことが分かりました。そうとは言え、また買いに行くのは面倒なのでガッシュで塗ることにしたのです。 初めて焼かない粘土を使ってみたのですが、製作方法に改良の余地はあるものの、面白かったです。子供でも扱え、ちょっとした工作をして楽しむのも良いですね。   因みにフシギダネ鉢には100円ショップで買った多肉植物のブルーサプライズと言うエケベリア属の植物を植えました。それから、マミラリアと言うサボテンも買ってみました。こちらは型取りに使った瓶に入れてみました。 鉢も瓶にも水抜き穴が無いので、植え付けにはハイドロボールと言う人工の土を使ってみました。植え付けに際しては、植物の根に付いた土を落とすのですが、その際に根が切れてしまったのでちょっと心配です。様子を見ながら育てていきたいと思います。  |
||||
【PR】
|
| 夏本番 |
| 2025/7/25 |
|
春に株分けしたミョウガの蕾が4つ出たのでさっそく収穫しました。洗った後に1枚皮が外れていたので口に入れると、爽やかな香りと独特の苦味が口に拡がりました。暑い季節にミョウガの涼味は本当に合いますね。サラダや天ぷら、味噌汁の具にしても良いですが、まずは冷たい素麺の薬味にしようと思います。ストレートにミョウガが感じられるのが良いですね。 このミョウガですが、その苦味のため、子供はあまり好んで食さないですね。私が子供の頃もそうだったと思います。苦味を美味しいと感じられるには、一定量の経験が必要になるのだと思います。ゴーヤやビールの苦味にしてもそうですが、ある程度の苦味の経験がないと、美味しく感じられないようです。 苦味に関する研究から、口の中にある苦味受容体(苦味センサー)が苦味に反応し、体が反射的に苦味を拒否することが分かっていますが、それは人間だけでなく、他の哺乳類にも備わっているそうです。原始的な哺乳類である単孔類のカモノハシにも苦味受容体があることが分かっていて、しかも幅広い種類の苦味を検知できるそうです。そして、苦みの知覚と拒否反応はゲノム(DNA)に組み込まれているのが研究により分かっています。 そう考えると、苦みを美味しいと感じるようになるのはどうしてなんだろうと思ってしまいますね。経験を重ねることで獲得できると言われていますが、そこには安全性を前提として、体への効果と味覚の発達(多様化)があるのだと思います。ある意味、苦みの美味しさが分かることは大人になった証と言えるのかもしれませんね(笑)。  さて、我が家にハマクマノミがやってきて20日経ちますが、心配していた攻撃性の問題は解消されたようです。強い個体が弱い個体を追いかけることはほぼ無くなり、エサもしっかり食べています。それで、サンゴ石のレイアウトは元に戻しました。弱い方は行動範囲が狭いようですが、ツガイになればもっと動きまわるようになると思います。 因みに自然下では、縄張りを守るメスの遊泳範囲は広いのですが、オスはそれほど広くはありません。スノーケリングやダイビングでクマノミが近寄ってきて齧られた経験をした方もいると思いますが、それはメスの仕業です。オスはイソギンチャクにすぐに隠れられる距離をキープしていますね。 梅雨が開けて夏本番です。   |
| 【PR】 |
| ブラックベリー |
| 2025/7/18 |
|
ブラックベリーが実っています。今年は昨年ほどではないですが、7月に入ってから毎週片手に一杯ほど収穫しています。主に休みの日に獲っているので、熟しすぎて落ちてしまった実もありますね。 ブラックベリーは獲るタイミングがとてもシビアで、実を指で摘まんで軽く引っ張るとすっと取れるものでないと酸っぱくて美味しくありません。見た目は黒く熟しているように見えても、無理に取らずにすっと外れるまで待たなければならないのです。なので、一度に収穫できる量が少ないのですね。 当初はブラックベリー酒を作ろうかと思っていたのですが、桑の実とラズベリーそして梅を漬けたので余分の保存瓶が無く諦めました。ジャムにしても良いのですが、以前の記事にも書きましたが、そのままだと種が気になり裏漉しする面倒があるので、今年は取れたてのフレッシュな実をそのまま食しています。甘酸っぱくて美味しいですよ。 7月終わりごろまで楽しめると思います。  さて、桑の実とラズベリーをお酒に漬けましたが、何かと用事があって、漬けた実を2週間後に取り出せずにいました。ようやく取り出したのですが、桑の実は1.5ヶ月、ラズベリーは1ヶ月漬けたことになります。 容器から実を取り出してみると、崩れた感じはなく原型を留めていました。なので、取り除いた後のお酒に濁りは殆どなく安心しました。試しにお酒を口に含んでみると、まだまだアルコールが尖っていたので、もう少し熟成させます。9月には飲み頃になると思います。 取り出したラズベリーの実はジャムにしました。 成分が抜けているので、コクを出すためにグラニュー糖以外にサトウキビ糖を加えて作りました。煮込んでいくと薄かった色が凝縮されて濃くなりました。レモン汁を少々加えると味が引き締まります。味見をすると、フレッシュなままジャムにしたものよりはコク(果実味)が少ないように感じましたが、それでも美味しかったです。 桑の実の方もジャムにしようと思ったのですが、適当な瓶がなく、タッパーに入れて冷蔵庫で保管しました。冷凍保存でも良いのですが、アルコール漬けなので日持ちすると思い、必要量取って甘いソースにしてお菓子に添えて食べようと思っています。   |
| 【PR】 |
| ハマクマノミ |
| 2025/7/11 |
|
住人のいなくなった水槽を清掃して3ヶ月ほど経ちますが、再び海水を入れて、ハマクマノミ2匹を迎え入れました。 当初は日本の淡水魚を考えていたのですが、アクアショップで探してみるものの、心を動かすような出会いがなく、海水魚を見ていたところセジロクマノミがいて飼育してみたくなりました。 その時にはまだ水槽をセッティングしておらず、サンゴ砂を敷いて海水を投入し、ろ過システムに海水を1週間巡回させました。 そして1週間後にアクアショップに行ったところ、目当てのセジロクマノミの姿はありませんでした。 落胆しつつも、他に何かいないか探してみたのですがこれと言ったものは見つからず、そろそろ帰ろうかと思った矢先でした。店員の方がバックヤードから生体の入った袋を幾つも出してきたのです。試しに見てみると、そこに2匹のハマクマノミを見つけました。体長7cmぐらいの同サイズでした。これも何かの縁と思い、2匹を購入することにしたのです。ハマクマノミはカクレクマノミより大きなクマノミで、体高があり丸い感じが可愛いですね。  自宅に戻って2匹を水槽に入れたのですが、最初は仲良く泳いでいるように見えていたのが、クマノミの性格上、1匹が縄張りを主張し始めました。 その結果、もう1匹の方は水槽の隅に隠れるように身を寄せるようになってしまいました。そうとは言え、しつこく追いかけ回すことはあまりないようなので、もうしばらく様子を見ることにしました。 念のため、組んでいたサンゴ石のレイアウトを替えて、岩場を2つにしました。空間を空けることで逃げ場所を増やす狙いです。その効果なのか、強い個体が弱い個体に近づいても、アタックする回数が減ったように見えます。もしかしたら、既に優劣が付いてしまっていることで、アタック頻度が減っているのかもしれません。 観察して気付いたのですが、弱い個体の体色が購入した当時よりも明るいオレンジ色に変わってきました。体色を明るくすることで強者の攻撃衝動を弱めているのではないかと推測しています。自然下のカップルのオスや小さな幼魚はオレンジ色であることからそう考えました。ハマクマノミの体色の変化についての論文などは見つかりませんでしたが、ホルモンの影響を受け、そうなるのではないかと思います。縄張り意識が高くなる(攻撃性が強くなる)ホルモンが分泌されると体色が黒くなるのだと思います。 大きさが同じぐらいの2匹の優劣が確定したことから、今後、強い方が体を大きくしてメスに、弱い方がオスになっていくと思われます。 強い攻撃性が見えた場合は隔離を考える必要があるのですが、4日後には弱い方も水槽の中をゆったり泳ぐ姿が見られたので、たぶん隔離しなくても大丈夫ではないかと思っています。仲良くペアになると嬉しいですね。  |
| 【PR】 JTBえらべるギフトに新商品登場! 海外・国内各地のグルメや雑貨を掲載したカタログ式ギフト「ぐるめふらいと」 世界各地の味を再現するレシピつきで、美味しいものや旅行が好きな方へのプレゼントにぴったり。 選んで交換した後もレシピ本として活用できる新しい形のカタログギフトです。 |
| ウィスキーが美味しくなる棒 | ||
| 2025/7/4 | ||
|
前回の記事でお伝えしましたが、「ウィスキーが美味しくなる棒」を安価なウィスキーに入れてみました。 この棒は「熟成スティック」と呼ばれており、酒樽などに使われている木材をスティック状に加工した棒です。ミズナラを使った物が多く、「ミズナラスティック」と呼ばれています。ミズナラ以外にはサクラやヒノキ、クリやカエデなどもあるようです。 因みにミズナラ樽はジャパニーズウィスキー独特のもので、他国のウィスキーとは異なる風味をウィスキーに与えています。その個性が世界的な評価を得る一端になっていると言えます。  試しに私が購入したのはミズナラスティック3本入りのものです。一度1本を1週間ほど安価なウィスキーに浸けてみたのですが、それほど違いは感じられませんでした。 試しに私が購入したのはミズナラスティック3本入りのものです。一度1本を1週間ほど安価なウィスキーに浸けてみたのですが、それほど違いは感じられませんでした。それで、もう一度ウィスキーを買ってきて、それにスティックを2本入れて3ヶ月浸けてみることにしたのです。そして、丁度3ヶ月経ったので試飲することにしました。 比較対象に予め同じ銘柄のものを用意しておきました。瓶を透かして見ると幾分スティックを入れた方が色が濃いようでした。蓋を開けて香りを嗅いでみると、当然ですがスティックを入れた方から木質の良い匂いがしてきました。香りは薄めで、想像していたほどではありませんでした。しかし明らかにスティックを入れていないものとの差が感じられました。 それから、味の違いが良く分かりようにストレートで飲んでみることにしました。それぞれショットグラスに入れてみると、液体量が少ないためか色の違いははっきりわからず、それほど見た目は変わりませんでした。 最初にスティックを入れていない方を飲んでみると、舌の上で尖ったアルコールの刺激を感じました。安価なウィスキーにありがちですね。 次にスティックを入れた方を飲んでみました。驚きました。アルコールのツンツンした刺激が抜けてまろやかになっていたのです。角が取れ飲みやすくなっていました。この変化にはびっくりしました。これが樹(樽)の成分の効果なのですね。その違いは明らかで、別物になっていると感じました。 しかし、これが美味しいウィスキーかと言うとそこまでではなく、飲みやすくなったと言う印象です。舌触りの変化は驚くほどでしたが、それで各段に美味しくなったとは感じませんでした。美味しいウィスキーは良い香りが鼻に抜けるのですが、それが無かったからです。 そうとは言え、この変化は特筆すべきで、前回記事で紹介した論文を証明してみせた事象でした。 ここで気付いたのですが、ウィスキーに入れる前にスティックを焼くと良いとのユーザー投稿がありました。もともとスティックには格子模様に焼き目が付いているのですが、さらに焼くことで風味が増すと言うのは想像できました。また実際にウィスキー樽は内部を焼き入れることで風味付けをしています。この工程はチャーリングと言われていて、焼くことで樽材の成分を分解し、ウイスキーに溶け込ませることで、香りやタンニンなどのポリフェノールを付加することを目的としています。 それで私もスティックを焼いてみることにしたのですが、焦げ目はあまりつかない程度に表面をさっと炙るぐらいにしたのです。しかし、それでは焼きが足らなかったようですね。もう少ししっかり焼けばもっと風味が出たと思うのです。 スティックは3本入りで、使っていないものが1本あり、また2~3回は再利用できるようなので、スティックの焼付け行程を見直し、再度実験したいと思います。 ウィスキーがまろやかに変容したことが分かっているので、それに香りとコク(ポリフェノール添加)が加われば美味しくなる予感がしています。スティックの焼き付け程度によって風味は変わると思いますが、焼き加減は試してみるしかなく、そこは個人の好みと経験を重ねるしかないと思います。 でも、なんだか楽しくなってきました。自分でお酒を育てるのもなかなか面白いですね。 さて、今夜は香りは少ないけれどまろやかになったウィスキーを飲むとしましょう。 「スランジバー(Slàinte mhath)!」  |
||
【PR】
|
| お酒の熟成 |
| 2025/6/27 |
|
仕込みから3ヶ月経ったので「清見オレンジ酒」を飲んでみました。オレンジの香りが口一杯に広がり、甘すぎず少しの苦味があり、なかなか上品な出来栄えでした。 飲み方はロックでもソーダ割でも良いですね。飲みやすくすいすいいけるので、飲み過ぎには注意しなければならないですね(笑)。  さて、使う果実(切り方)によって熟成期間は変わりますが、これまで作った果実酒は約3ヶ月の熟成期間を経てから飲むようにしています。漬けてから2週間後くらいから飲めると大方のレシピ情報には書いていますが、3ヶ月待つだけで口当たりが全然違ってくるのです。お酒が若い内はアルコールの刺激が強く感じられますが、3ヶ月後はまろやかになっているのですね。 さて、使う果実(切り方)によって熟成期間は変わりますが、これまで作った果実酒は約3ヶ月の熟成期間を経てから飲むようにしています。漬けてから2週間後くらいから飲めると大方のレシピ情報には書いていますが、3ヶ月待つだけで口当たりが全然違ってくるのです。お酒が若い内はアルコールの刺激が強く感じられますが、3ヶ月後はまろやかになっているのですね。成分的にはそれほど変わらないと思うのですが、何故なのか不思議に思い調べてみることにしました。 ネット検索で調べてみると、すぐに多くの情報がヒットしました。その中で、とても興味深い論文に出会えました。 北条正司氏の「水とアルコールの化学―酒類の 「熟成」の謎を解き明かす」という論文です。 氏によると「熟成した酒」の中では、水とアルコール間の相互作用が強くなっているという考えは、酒の熟成を研究している化学者によって共有されている概念だそうです。 その前提で、「有機酸(およびアミノ酸)と ポリフェノール類が「酒の熟成」に対し、重要な効果を与えることがわかってきた。熟成感の達成に必要とされる時(経過)は 第一次的に重要ではなく、副次的なものでしかないことが明らかになったのである。言い換えると、水―エタノール混合物が飲料可能(または飲みやすい)状態に変化するには、時間経過が必須な場合もあるが、全ての場合に当てはまる条件ではない。」と記されていました。 そして、最終的な結論として「酒をまろやかに変化させる、すなわち、酒としての熟成感を付与する、または酒を「水―エタノール混合物」から隔てるためには、十分量のプロトン(水素イオン)供与体または受容体の共存を前提条件にして、時間経過を必要としない。醸造を含めた酒の熟成は、(時間経過に伴なう)化学成分の変化によって達成される。」とありました。 面白いですね。熟成には化学成分の変化に必要な時間が重要と言うことなのです。つまり、化学変化が止まったものを長く保存していても意味がないと言うことですね。 論文中にはウィスキーの熟成について記されている部分があって、「樽中の保存年数が全く同じでも、熟成樽の種類により中のウイスキーの熟成度が全く異なることである。何回も使い古した旧樽中では、20年以上保存してもあまり着色せず、酸度や総フェノール量が極端に低いままであり、熟成はほとんど進んでいないのである。」とありました。 それで思い出したのが、ずっと以前になりますが、「瓶詰にしたウィスキーは何年保管しても、それ以上には熟成しない」と聞いたことです。その根拠が分からずにいたのですが、樽の成分が添加されないことから熟成は止まると言うことだったのですね。誰から聞いた(もしくは本で読んだ)のか覚えていませんが、たぶんそれは経験則からで、科学的な見地からのものではなかったような気がします。 なお念のため、論文には「私が提案した学説は、単に、ある一方向から見た 「お酒の飲みやすさ」を説明しているに過ぎず、必ずしも全般的な「おいしさ」の原因を明らかにしたという訳ではではない。」と記されていることもお伝えしておきます。 そうとは言え、私はかなり腑に落ちました。 果実酒に関する情報や私の経験則から、3ヶ月の熟成が必要としていましたが、今となっては、2週間後に果実を取出すことで、果実成分の供給が止まり、自宅での保管環境から液中成分の化学反応に要する時間が3ヶ月程度であったのだと思います。もしも、3ヶ月後にも未反応の成分が残っていれば熟成は進むことになりますね。 実は昨年作った桑の実酒を1瓶残していて、今年熟成させている桑の実酒と味比べをしてみようと思っています。その結果は後日(9月以降)報告しますね。 さらに考察ですが、2週間後に果実を取出さないでそのまま漬けておいた場合、味を左右させる雑味成分が必要以上に増加することも考えられます。例えばオレンジであれば房のセルロースなどが考えられますね。繊維がほどけて濁ったり口当たりが悪くなったりするのではないかと思います。果実を入れっ放しにした結果、そのようになった事例などがブログなどに載っているのを見掛けました。レシピ情報は先人達の経験則からくるものであり、たぶんそれは正解なのだと思います。経験則の裏側には必ず科学的根拠が潜んでいますからね。(別の意味で、根拠のない個人の経験則だけで物言う人もいますけどね) 知っている限り、唯一「梅」だけは違っているようですね。梅は完熟していない青梅を使うことがミソのように思います。梅酒は梅をずっと漬けていると時間とともに熟成が進みます。丸のまま皮に覆われていることで、成分の溶けだす期間が長いのだと思います。梅を漬ける期間がどのくらいが良いのかは分かりませんが、もしかしたら梅の大きな種が熟成期間を長くする要因なのかもしれませんね。 さてさて、桑の実酒の飲み比べは未だ先ですが、実はウィスキーが美味しくなると言う棒(ミズナラスティック)を購入し、安価なウィスキーに浸けています。 3月に購入し一度漬けてみて、2週間後から違いが出るとされていて飲んでみたのですが、あまり違いが分かりませんでした。なので、再度ウィスキーを買ってきて、スティックを2本に増やして浸けています。もうすぐ浸けてから3ヶ月になるので、そろそろ味を試してみたいと思っていたところです。 上記の論文にあったように、樽の成分を加えることによって熟成されるのであれば、きっと美味しくなっているはずですね。我が身をもって実験です。 結果は次回に報告したいと思います。 〇参考 J-STAGE 水とアルコールの化学― 酒類の 「熟成」の謎を解き明かす ※「科学技術情報発信・流通総合システム」(J-STAGE)は、国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) が運営する電子ジャーナルプラットフォームです。J-STAGEは、日本から発表される科学技術(人文科学・社会科学を含む)情報の迅速な流通と国際情報発信力の強化、オープンアクセスの推進を目指し、学協会や研究機関等における科学技術刊行物の発行を支援しています。  オレンジ酒のハイボール(炭酸水割) |
| 【PR】 |
| 初夏の収穫 |
| 2025/6/20 |
|
今年はラズベリーがたくさん収穫できています。 1回目の収穫では両手一杯分の実が取れました。生食用に1/3ほど食べて、残りはラズベリー酒として漬けてみました。作り方はこれまでと同様に果実と氷砂糖を入れた保存瓶にホワイトリカーを入れました。ラズベリーがそれほど多くないので、2リットルの保存瓶を使いました。このまま約3か月保管し熟成させます。 2回目の収穫時にはジャムを1瓶作りました。ラズベリージャムは子供たちも大好きです。爽やかな酸味と甘さでとても美味しいですからね。クラッカーを土台にしてたっぷりのクリームチーズと、その上からジャムを乗せると簡単で美味しいレアチーズケーキ風なデザートになりますよ。ラズベリーはまだ収穫できそうなので、ジャムをもう1瓶つくれそうです。   桑の実(マルベリー)は今年も大量に生っています。こちらは4リットルの保存瓶で桑の実酒を仕込みました。ジャムも3瓶作りましたよ。 桑の実はスーパーフードと言われているのをご存知でしょうか? 私は桑の木を植えた時には知らなかったのですが、調べてみると豊富な栄養素を含んだ果実なのですね。でも、そのままでも食べられるのですが、食べなれた果物に比べると、甘味が少なくぼんやりとした味で好んで食べたい気にはなれないですね(※個人的な感想です)。 健康や美容のためと割り切って食べるのも良いですが、果実酒やジャムなどに加工して美味しく食べるのがお勧めです。 それでも個人宅で食べるには多すぎて、落ちた実を掃除するのがこの時期の日課になっています(笑)。 ブラックベリーはまだ実は緑色ですが膨らんできました。こちらもたくさん出来そうです。 そうそう、庭に植えてあるサクランボの樹(紅きらり)ですが、今年は4粒収穫できました。今年の目標であった家族分の収穫を達成しました(笑)。今後、年を追うごとに収穫量が増えることを期待しています。 写真は2粒ですが、これより前に色付いた2粒を採取しました。サクランボは上品な甘酸っぱさでとても美味しかったです。  |
| 【PR】 |
| 絵本(電子書籍) | ||||
| 2025/6/6 | ||||
|
何度かGIMP(画像編集ソフト)を使って絵本を作成していると記していましたが、新書がようやく完成しました。 今回もサイが主人公で、親離れしたサイのお話です。 題は「あるいていたら」とし、英語版は「WALK ABOUT」です。このサイト名は「WALKABOUT」ですね(笑)。 「walk about」は「歩き回る」と言った意味ですが、「walkabout」と繋げると、名詞としてオーストラリアに住むアボリジニの青年男性が長い旅に出て原野で生活する通過儀礼のことを意味するものになります。 この言葉を知ったのは、サイト名を付ける時だったと思います。サイトは2003年に立ち上げたので、初めてオーストラリアに行った2005年よりも前ですね。当時、時間とお金があれば海外旅行に出掛けていて、その頃の自分の気持ちとWALKABOUTと言う言葉が重なるように感じてサイト名にしたのです。 今でもサイト名をこの言葉にして良かったと思っていて、とても気に入っています。 もう青年期はとっくに過ぎてしまった私ですが、まだWALKABOUTしているような気がします。 さて、新書の「あるいていたら(WALK ABOUT)」から、2枚の原画を掲載します。 アフリカの大地を感じて貰えると嬉しいですね。 【お知らせ】新書(「あるいていたら」「WALK ABOUT」)について 本日より無料キャンペーンがありますので、興味のある方はぜひダウンロードしてみてください。 ☆キャンペーン期間:6/6(金)16時~6/11(水)16時   |
||||
【PR】
|
| アリウム |
| 2025/5/30 |
|
11月に植えたアリウムの花が咲きました。 5月初旬に咲いたのは、アリウムグローブマスターという品種で大きな丸い薄紫色の花を咲かせました。 なかなか見応えのある大きな花(花の集合体)で、直径20㎝ぐらいあり、1株に3本の花が付いていました。通常は、球根1個に対して花一つなのですが、たぶん購入した球根が内部で分球していたのだと思います。 アリウムギガンチウムも植えていたので、それが開花したらグローブマスターと一緒に写真に撮ろうと思っていたのですが、開花した時にはグローブマスターの方は花枯していました。   ギガンチウムの球根は購入した時点で既に二つに分球していたので、分けて植え付けしました。 先に芽を出したのはギガンチウムだったのですが、開花はグローブマスターよりも遅かったですね。 花は分球したためか小さめで直径10cmぐらいでした。球根の状態が良いと直径15cmぐらいの花を咲かせます。花の色は濃い紫色で、丸い花が可愛いですね。  どちらのアリウムも綺麗で大きく可愛いらしい花で庭が華やぎ、目を楽しませてくれます。 花が終われば、花茎を切り、球根を育てるために葉が黄色になるまで植えておきます。 梅雨入り前までには球根を掘り起こして保管し、晩秋(11月頃)になったら、また植えたいと思います。 小型の白い花が咲くグレースフルビューティーという種類のアリウムも咲きました。 ただ、こちらは花茎がまっすぐに伸びずにぐにゃぐにゃしていて、しかも咲いた花の重みに耐えられずに、花が地面に着いてしまったものもありました。 調べてみると、この種はどうやらそのように成長するようです。花はとても可憐で可愛いのですが、全体はまとまりのない印象がしました。プランターや鉢植えの方が向いているかもしれませんね。 満開の美しいフォルムの写真を撮りたかったのですが、気が付いた時は既に枯れ始めており、タイミングを逸してしまいました。なので、残念ながらグレースフルビューティーの写真はなしです。 |
| 【PR】 |
| バッグのサイドポケット修理 | ||||
| 2025/5/23 | ||||
|
カメラバッグとして使用していたショルダーバッグのサイドポケットについていたドローコードが切れてしまい、いつか修理しようと思いながら2年以上経過していました。 ジーンズのリペアで裁縫したこともあって、ようやくそれに手を付けることにしました。 ドローコードはサイドポケットに入れたペットボトル等がずり落ちないように留めるためのものです。バッグを点検してみると、切れたコードの端が残っていて、コードはバッグ本体にミシン掛けでとめられていることが分かりました。同じように修復するにはバッグを解体する必要があり自分では無理なので、新たに付けるコードをサイドポケットのコードを通しているカバー(布)に縫い付けることにしました。 初めに切れて残ったコードをラジオペンチで引き抜きました。コードは糸で縫い付けられておらず、コードを跨いだ糸で押さえとめられていたので、引き抜くのに力を要しましたが、バッグにダメージを与えずに取ることができました。  次に購入したドローコードを必要な長さに切り取り、それにコードストッパーを通しておきます。コードの両端を縫い留めるので、最初にそうしていれば通し忘れることはないですからね。 次に購入したドローコードを必要な長さに切り取り、それにコードストッパーを通しておきます。コードの両端を縫い留めるので、最初にそうしていれば通し忘れることはないですからね。元々のストッパーと形状が違うのですが、保管していた場所を忘れてしまい、コードとストッパーがセットになっている商品を購入して、そのストッパーを使いました。機能的には同じなので気にするほどでもないですね。 コードの一端をサイドポケットの通し穴に入れ、先端がバッグ本体に届くまで差し込みます。それから、コードの根本(端)付近をカバー布と一緒に縫いとめます。コードがすっぽ抜けると困るので、コードにも針を通して縫い付けました。もう一方も同じように縫いとめ、最後にコードエンドストッパーを留めて完了です。 補修跡が少し気になりますが、おおむねイメージ通りに修理できたと思います。 実際にペットボトルを入れてみましたが問題ありませんでした。   このショルダーバッグはAbu Garciaと言う釣り具メーカーのものなのですが、たすき掛けすることを前提として作られているようで、体をホールドするように太目の肩ベルトが付けられています。個人的な意見ですが、たすき掛けにするととても安定感があり、移動しても疲労が少ないように感じます。また、肩に掛けたままで物の出し入れがし易いのも良いですね。見た目もとても気に入っています。 私の持っているバッグは旧型で、現行タイプは生地の防水性の向上、肩パッド付、サイドポケットはコードではなくゴムバンドになっているなど違いがあるようですね。  |
||||
【PR】
|
| ジーンズのリペア(つづき) |
| 2025/5/16 |
|
EDWINの補修したジーンズを正味1週間ほど履いたのですが、貼ってあった接着芯が破れて穴が空いてしまいました。ジーンズのリペアで参考にした多くのサイトでは接着芯だけを使っていたので大丈夫なのかと思っていましたが、そうではありませんでした。厚手の接着芯を使ったとは言え、貼る際もこれだけで本当に大丈夫なのかなと思っていたので、想像通りの結果になってしまいました。膝や肘などの引っ張られたり、摩擦の多い箇所の補修は接着芯だけの補修は難しいようです。それで布製のパッチを当てることにしました。 最初に貼っている接着芯を穴の部分を残して剥がしました。その後で、今回できた穴を塞ぐために、残した接着芯と一緒にジーンズの繊維を縫い留めました。それから、裏側から穴を覆うように布パッチを当て、アイロンで圧着して完了です。圧着してから縫っても良いのですが、当てる布が固い場合は接着芯で固定して縫い、その上から布をあてがう方が楽にできます。たぶん、私が使っている「糸が簡単に通る針」だと、固い布を通した時に糸が針から外れる可能性が高いので、接着芯を使って破れ箇所を整えるのは良い方法だったと思います。 見た目は前回補修時と変わりませんが、裏返すとしっかり布で補強されているのが分かりますね。これでしばらく様子を見たいと思います。もしも当て布が剝れてくるようであれば、当て布を糸で縫い合わせようと思います。      さて、話は変わりますが「オレンジジャム」を作りました。 清美オレンジ酒の仕込みをしていましたが、漬け込んでいた果肉を取り出したので、それを使いました。また、清海オレンジが10個ほど残っていて、時間が経ったことで皮に黒いシミのような斑点が沢山できていました。子供たちは食べようとしないので、それも使うことにしました。 黒い斑点のあるオレンジをナイフで切ってみると、瑞々しい果汁たっぷりの果肉が現れました。皮が固いおかげなのか、見た目と違い中身は全く問題がありませんでした。 美味しそうだったので、そのまま5個を食べて、残る5個をジャム用にしました。 清美オレンジのジャムに加工するにあたり、今回は皮は入れないことにしました。皮にシミがあるので見た目が悪くなりそうだったからです。水分の多い果物はジャム向きではないと言われますが、じっくりと水分を飛ばしていけばジャムになります。 鍋にざっくりと刻んだ果肉とグラニュー糖を加えて煮ていきます。とろみが出てきて、しゃもじで鍋底を引くと筋が現れるようになれば完成です。 色鮮やかなオレンジジャムが出来ました。  |
【PR】 |
| 階段ひび割れの修理 |
| 2025/5/9 |
| 随分前になりますが、大きな地震があった時に、玄関前の階段にひび割れが出来ていました。業者に見てもらい、ひび割れ部分を覆うようにコーキングシールしてもらったのですが、コーキングが経年劣化して割れてきてしまい、たぶん隙間から水が侵入してひび割れも大きくなってきているように思えました。このまま放置する訳にもいかないので、自分で隙間を塞ぐことにしました。 初めに割れたコーキングを剥がしていきます。一部に綺麗に剥がせないところもありましたが、隙間が塞がれば良いので気にしません。隙間をハンディライトで照らしてみると、階段の段差の継ぎ目部分のコンクリートが綺麗に割れているのが見えました。割れ部分の両面ともコンクリートであることが分かり、モルタルを流し込んで割れを埋める方法で修理できそうです。   修理材として流し込むタイプのモルタルがあり、それは流動性があるので、流し込んでいけばほぼほぼ水平に拡がっていきます。なので、コテなどを使わずに表面を平らにすることができるのです。また流動性があることから、細かな隙間に流れ込んで空洞ができにくいのも選定した理由です。 因みに流動性があるので壁のひび割れなどの修理には向いていません。その場合はもっと粘着性のあるものを選ぶと良いですね。 「流し込みモルタル」と言う商品と、ビニール製の注入袋を購入しました。注入袋とは三角錐の袋で尖端を切って使います。ケーキ作りのホイップ絞り袋と同じ要領です。 「流し込みモルタル」はバケツなどの容器にモルタル粉末と規定量の水を入れて良くかき混ぜ練れば準備完了です。 練ったモルタルをひび割れに流し込んで行きます。初め注入袋を使って流し込んでいたのですが、大き目の粒が尖端部分に詰まってしまうので、途中からバケツからそのままひび割れに注ぐことにしました。ひび割れからはみ出た物はスコップを使って割れ部分に戻し入れることで対処しましたが、その方がストレスなくスピードも早かったです。 モルタルは約2時間後に硬化するので、その間にはみ出したり零れたりしたモルタルを水でざっと流します。修繕箇所以外の不要なモルタルが塊状に硬化するのを防ぐためです。水でモルタルの粒をばらばらにすることで、乾いた後は砂と同じようにホウキで履いて掃除できます。 素人作業ですが無事にひび割れの修理ができて一安心しています。  |
【PR】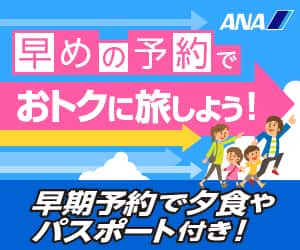 |
| ジーンズのリペア |
| 2025/5/2 |
|
膝部分が破れてしまったジーンズが4本あったので、リペアしてみることにしました。 3本はイオンなどで売られているストレッチ素材の物で、アイロンで付けられる専用の補修パッチが100円ショップなどで売られており、それを買ってきて、ジーンズの裏側から圧着しました。簡単に破れ箇所を塞げるので手軽で便利ですね。 残る1本はEDWIN404でゆったりめのものです。以前にブラッド・ピットが宣伝していた503は私の体型では太腿部分が細くて履けず、403か404を愛用していました。今手元にあるEDWINは403と404の各1本ずつだけで、その内の1本です。 このジーンズは独身時代の最後の一本で、ケニアやスイスなどにも一緒に行った旧友のようなものです。膝の破れが大きくなってきてから、履かずに衣装ケースに入れたままになっていました。何度か古着を捨てていたのですが、まだ履けそうなので捨てずに取っておいたのです。 高価なビンテージ物ではありませんが、愛着があるのでアイロンでパッチを貼って終わりではなく、もう少し本格的な修復をしてみようと思いました。 Webでジーンズのリペア方法を調べてみると、ミシンを使わずに手縫いでも出来ることが分かりました。我が家にミシンはあるのですが、私は小学校の家庭科の授業以来ミシンを使ったことがなく、1から思い返して準備するのは面倒だったので、手縫いをすることにしました。妻にミシン掛けをお願いすることも出来ましたが、それよりも自分でやってみたかったからです。 裁縫道具は妻が持っているのですが、私は遠視(老眼)なので針に糸を通すのが難しく、100円ショップで糸通しなど売っていないか行ってみることにしました。すると、何と「糸がかんたんに通る針」なるものが売っていたのです。針の頭が割れていて、張った糸を上から割れ目に押さえつけると針穴に入る仕組みになっていました。これは便利かもしれないと、すぐにそれを買って帰りました。 それから接着芯と言う不織布で片面に接着剤が塗られている布を買いました。これは100円ショップでも売っていたのですが、今後も使うかもしれないので、Amazon で厚手の大き目の物を購入しました。大きさから換算すると、100円ショップのものよりも割安になりました。接着芯は必要分だけ切取って使います。 接着芯は補修パッチと同じようにアイロンでジーンズの裏地に張り付けます。これで終了しても良いのですが(補修パッチと同じ使い方ですね。)、針と糸を使って破れた部分を縫い合わせて行きます。You Tubeで見つけた「ジーンズの穴を手縫いでお直し」を参考にして、「返し縫い」と言う縫い方で破れた部分を縫って行きました。かなりいい加減に縫ったのですが、糸が切れたり、針から糸が外れたり(当該針は簡単に糸が通せる分、テンションが掛かりすぎると糸が外れてしまうことがあるようです)を繰り返しながら、両膝2ヶ所の補修に正味5時間程度掛かってしまいました。たぶん、慣れている人ならそれほど時間は掛からないのだろうと思います。 それでも自分で補修したジーンズをまた履けるのが嬉しくなりました。縫っている間は、それだけに集中して無心になっている自分がいて、何だかそれも新鮮に感じました。自己満足の世界かもしれませんが、ある意味達成感みたいなものを感じましたね。手縫いの拘りは、たぶん履いていたジーンズへの愛着とこの達成感にあるのだと思います。そして、手を加えるごとに愛着が増すのでしょうね。 今では業とリペアしたようなジーンズも売られているようですね。ファッションには疎いのでわざわざそれを購入することは無いと思いますが、今のジーンズがまた破れたら、リペアしてみようと思います。 その前に、ミシンの使い方を覚えた方が良いような気がしていますが…(笑)。       |
| 【PR】 |
| ミョウガの株分け |
| 2025/4/25 |
|
2月に鉢植えしていたミョウガを株分けしました。 鉢からミョウガを掘り起こそうとしたのですが、地下茎がぎっしりと踏ん張っていて、なかなか鉢から取り出せませんでした。そのため、スコップで茎を切りながら取り出しました。 土を落とした地下茎を15㎝ほどに切り分けて株分けすると4株ほどになりましたが、これまで使っていた鉢と、大き目のプランターが空いていたので、2株だけを残して他は燃えるゴミに出しました。ミョウガは繁殖力が強いので地植えはしたくなかったからです。 新しい土を鉢とプランターに入れ、株分けしたミョウガの地下茎をそこに埋めれば作業終了です。 それから約2ヶ月が経ち、鉢とプランターの両方にようやくミョウガが芽吹いてきました。なかなか芽を出さないのでやきもきしていましたが、温かくなったことで発芽したようです。ミョウガは地温が15℃前後になると発芽するそうです。 今後順調に育ち、夏に蕾を収穫できると嬉しいですね。  |
| 【PR】 |
| ホウボウの干物 |
| 2025/4/18 |
|
スーパーでホウボウを見つけて買ってきました。 ホウボウは良い出汁が出るので、アクアパッツァやブイヤベース、鍋物にしても美味しい魚ですね。当初、アクアパッツァにして食卓に出そうかと思ったのですが、いつものごとく肉食系の下の子から却下されてしまいました。(夕食は鶏肉のトマト煮になりました) それで、日持ちする一夜干しにすることにしました。頭と内臓を取った下処理されたものだったので、身を開く作業だけでゴミも出ずに助かりました。 そうとは言え、ホウボウの頭からは良い出汁が出るので、スープや鍋物にする時にはお頭付きの方が良いですね。また内臓の「浮袋」はなかなかの珍味でとても美味しいですよ。浮袋をさっと茹でてポン酢で食べても良いし、勿論煮物の具材として入れても良いです。食感は弾力があり肉のような感じがします。まだ食べたことのない方は一度お試しあれ。本当に美味しいですよ。他に胃袋や卵、白子も食べられます。 なので、もしも新鮮なものだったらそのまま買ってきて自分で下処理するのも良いと思います。お店に下処理をお願いできれば良いのですが、さすがに内臓の可食部だけを取出してくださいとは言い難いですからね(笑)。 ホウボウは背開きにして、塩水に2時間ほど漬けてから陰干しにしました。15時から翌朝の9時頃(約18時間)まで干しました。身を触ると、指にくっつくような弾力感があり、丁度食べ頃だと思います。水分を程よく保持しているのでふっくらと焼きあがり、味わいはこの状態がベストだと思います。   今年も時間と食材があれば魚の干物を作っています。アジ、イワシ、タチウオ、チカ、メヒカリを干してみました。 チカとメヒカリは小魚で初めて干してみたのですが、どちらも美味しかったです。 チカは見た目がワカサギに似ています。ワカサギは淡水や汽水域に生息していますが、チカは海に生息していて北海道や東北で獲れます。以前はワカサギとして売られていたそうですが、今は区別されています。ワカサギと殆ど変わらない淡泊な味で、天ぷらや唐揚げは定番です。 メヒカリはその名のごとく深海性の小魚です。正式名称はアオメエソと言います。こちらも天ぷらや唐揚げも美味しいです。身は脂肪分が多いので、食感はふわふわしています。 一夜干しにしてもその食感には違いがあり、チカは柔らかくもしっかりした身で、メヒカリはふわふわしています。 どちらも甲乙つけがたい味で、焼いた一夜干しに七見唐辛子を混ぜたマヨネーズを付けて食べると、お酒がついつい進んでしまいます(笑)。 |
| 【PR】 |
| 庭にある果樹の様子 |
| 2025/4/11 |
|
庭に幾つか果樹を植えていますが、春の訪れと共に開花や芽吹きだしました。 サクランボ(紅きらり)の花が咲きました。来週には満開になりそうです。 去年は風雨に晒されて落下したり、鳥に食べられたりして、結局、子供が食べた1個だけでしたが、今年は家族分は収穫したいですね。ほったらかしなので、あまり期待せずに待つとします。  ブルーベリーも小さな白い花が咲いています。後から植えた別種のブルーベリーはまだ咲いていません。受粉は虫任せなので、こちらも期待せずに待っていましょう(笑)。  ジューンベリーの花も咲きました。晩秋に枝を剪定したためか、いつもに比べて花の数が少ないような気がします。それでも片手一杯ぐらいは採れそうですね。  桑の樹(マルベリー)は秋に枝をかなり刈り込んだのですが、枝に沢山の花が付いているので、今年も沢山実りそうです。今年も「桑の実酒」を作りたいですね。  ラズベリーは新しいサッカー(地下茎からでる枝)が出てきています。昨年、元気が無くなっていたので心配していましたが、冬に追肥をした効果があったのか、このまま元気を取り戻してくれると嬉しいですね。多くは望みませんが、ジャム1瓶ぐらいは作りたいですね。  ブラックベリーは茎に緑色の小さな葉が芽吹いてきました。こちらは昨年豊作だったので、今年もそうなると嬉しいですね。沢山とれるようなら「ブラックベリー酒」を作ってみたいです。 (ブラックベリーの写真は撮り忘れてしまいました) |
| 【PR】 |
| 補修作業 | ||||
| 2025/4/4 | ||||
 日頃から使っているワンショルダーバッグのメッシュの背布が破れてきていました。それで破れが広がらないように補修しました。 日頃から使っているワンショルダーバッグのメッシュの背布が破れてきていました。それで破れが広がらないように補修しました。初め、針と糸で繕おうと思ったのですが、メッシュなのでテンションが掛かればまた破けてしまいそうで止めました。それで、補強も兼ねてパッチを当ててみることにしました。そこで、テントなどの補修用のナイロン粘着テープを購入し貼ってみることにしました。 破れた所は背布と底布を合わせた縫合部分だったので、パッチテープを大き目に切り取り、縫合部分を覆うように貼り付けました。 見た目もそれほど気にならずに補修できたように思います。耐久性が気になりますが、しばらく使ってみて剥がれるようであれば、布用の強力接着剤をパッチに付けて貼りなおそうと考えています。 今のところ問題なさそうですが、様子見ですね。 
  上記のパッチテープを探していると、靴用のパッチがあるのを知りました。普段履いているシューズの踵部分が擦り切れて破れそうだったので、試しにそれも買ってみました。 上記のパッチテープを探していると、靴用のパッチがあるのを知りました。普段履いているシューズの踵部分が擦り切れて破れそうだったので、試しにそれも買ってみました。私は普段履きに軽く通気性が良いランニングシューズを履いているのですが、大概ソールがダメになる前に踵部が破れてしまい、新たに靴を購入することを繰り返していました。その度に「まだ履けそうなのに」と思っていたので、試す価値があると思ったのです。 届いたパッチは上記の修理用パッチと違って、踵の接触面の手触りはソフトな感じがしました。早速貼ってみると、両サイドの擦り切れ部分を辛うじて被せました。もう一回り大きければ良かったですね。 パッチを貼ったシューズを履いてみましたが、特に違和感はなく問題なさそうです。後は耐久性ですが、これも様子見ですね。 庭仕事用などに踵の破れたシューズを何足か残しているので、それらにも貼れば外出用にも使えそうです。 
 (おまけ) 随分前に買った子トラの「ぬいぐるみ」があるのですが、お腹のおへその辺りの縫合がほどけて人差し指が入るぐらいの穴が開いていました。それを針と糸で適当に縫い合わせました。 これは私が独身の頃に買ったものです。「ぬいぐるみ」が好きと言うのではないのですが、これを見た時、あまりに本物と見違えるほどで欲しくなり購入したものです。その後、いつしか体の縞模様は褪せて消えてしまい、今では子ライオンになってしまいました(笑)。 子供が生まれた頃にはライオンになっていましたが、彼らが幼少の頃はそれと遊んだり、枕元に置いて一緒に寝ていたりしていました。なのでとても愛着のあるものなのです。 ぬいぐるみのお腹の縫合をした後、それを洗ってみることにしました。見た目はそれほど汚れて見えなかったのですが、買ってからまだ一度も洗ったことがなかったからです。 Webでぬいぐるみの洗い方を調べてみると、中性洗剤やシャンプーを使って洗えることが分かりました。 それでシャンプーを使って洗ってみることにしました。シャンプーをお湯に溶かして薄めた溶液でぬいぐるみ全体を軽くもみ込むようにして洗います。ただし水分が中深くまで沁み込まないように手早く行います。ぬいぐるみの詰め物(綿)が偏ったり固くならないようにするためです。 満遍なく洗えたらシャワーをかけて汚れを流していきます。これも手早く行いますが、意外だったのはそれほど汚れが付いていなかったことです。毛が化繊だったので汚れが付きにくかったのだろうと思います。どす黒い汚れが出てくると思っていたので拍子抜けしました。 汚れを洗い流してから、洗濯網に入れて洗濯機で脱水(ソフト)しました。それを日陰で干して終了です。 綺麗になったぬいぐるみですが、子供たちはもう遊ばないので、私の部屋に置いています。トラからライオンに変わりましたが、今見ても可愛いと思います(笑)。  |
||||
【PR】
|
| 清見オレンジ酒 |
| 2025/3/28 |
|
レモン、柚子と柑橘類のお酒を作りましたが、どちらもとても美味しく出来たので、今回は「清見オレンジ」を使った果実酒を作ってみることにしました。 清見オレンジは「ミカン」と「オレンジ」を掛け合わた品種で、スーパーの店頭でもよく見かけますね。皮はミカンより固いですが、オレンジよりも柔らかいので手で剥くことができます。果肉は濃いオレンジ色で果汁たっぷりで甘くとても美味しいですね。 その清見オレンジを5㎏ほど買ったので、その一部で清見オレンジ酒作りをしました。 作り方は他の柑橘類の果実酒とほぼ同じです。 材料 清見オレンジ 8個 ホワイトリカー 1800ml 氷砂糖 200g 保存容器(今回は4ℓの瓶を使用) ①清見オレンジの皮を剥きます。 ②皮(約1個分)の裏側の白い部分をナイフで削ぎ取ります。 ※白い部分は苦味が出るので取り除きます。皮には香り成分が多く含まれています。 ③実を切って容器に入れます。(果汁が出やすいように輪切りにスライスしました) ④③の上に氷砂糖を入れます。(果肉が浮かび上がらないように氷砂糖が重石の役割にもなります) ⑤④にホワイトリカーを注ぎ入れます。 ⑥②を容器に入れ蓋をし、冷暗所に保管します。 ⑦1週間~2週間後に皮を取出します。(香りが出ていたら皮を取り出します) ⑧2ヶ月後に果肉を取出し、果肉を濾して出た液を容器に戻し入れます。 ⑨3ヶ月したら飲み頃になります。 レモンの果肉を1個入れた方がすっきりとした味になりそうですが、初めて作るので清見オレンジだけにしてみました。 3月終わりに漬け込んだので、飲み頃を迎えるのは6月終わり頃ですね。初夏に爽やかなオレンジ風味のお酒を味わえるのが楽しみです。  |
【PR】 |
| アクアショップ |
| 2025/3/21 |
|
クマノミ水槽のコケ取りをしてもらうためにクマノコガイを入れていました。この巻貝は12年ほど前に家族で磯遊びをした時に持ち帰ったものです。それが1月の終わりごろに死んでしまったので、新たなコケ取り用の貝を入れようと思っていました。 家から車で20分ほどで海には出られるのですが、そこは湾岸がコンクリートで整備されており、磯がある場所まで行くのには近くても有料自動車道を使って1.5時間は走らないとたどり着けません。 磯に行けば巻貝は簡単に採取できるのですが、そのためだけに費用を掛けて行くのは気が引けていたので、久しぶりにアクアショップに行ってみることにしました。 飼育中のカクレクマノミを買ったショップが近くにあったのですが、コロナ渦に廃業してしまい、近所のホームセンターのペットショップにも観賞魚や水槽など売ってはいるのですが、さすがに海水の生体は扱っておらず、Webで調べて、ふたつ隣の市にあるアクアショップで海水魚を扱っていることが分かり行ってみることにしました。 余談ですが、今では通販で生体を購入できるようですが、やはり通販は見るまで分からないので不安になりますね。そのような訳で生体を探すのは、アクアショップに行くか、磯などで採取するようにしています。 ショップに行くと、最奥のエリアに海水コーナーがあり、そこに目的の巻貝を見つけました。1個150円、5個で498円と安く手頃な値段でした。貝殻にコケが付いて断定できませんが、種類はおそらくクマノコガイだと思います。それ以外に、綺麗な外観のコケ取り用の貝も何種類か売られていましたが、安いクマノコガイを選びました。前と同じ種類と言うこともありますが、店員さんに確認はしていませんが、近場で採取されたもののように思ったからです。 何故そう思ったのかと言うと、貝の入れられた水槽の脇に、近海魚が入れられた水槽があったからです。中を見ると、タカノハダイとカゴカキダイの幼魚やキヌバリ、カエルウオなどが入っていました。その中には1cmほどのボラと思われる稚魚まで入っていたのです。さすがにボラの稚魚を仕入れる業者はいないと思われ、会社のスタッフなどが磯で採取してきたと思うのです。そうだとすると、その磯にはクマノコガイが沢山いるはずなので、それもついでに採ってきて販売していると考えるのは自然な流れですね。 その日、クマノコガイを5個買って帰り、クマノミ水槽に入れました。 水槽に入れた貝は、すごい勢いで藻を食べています。空腹だったのかもしれません。珊瑚岩に付いた藻を齧り取った跡が見えるので直ぐに分かりますね。 水槽のバランスが取れ、貝も長生きしてしてくれたら嬉しいですね。  ※沖縄 渡嘉敷島にて撮影 |
| 【PR】 |
| 折りたたみ自転車 | ||
| 2025/3/14 | ||
|
折りたたみ自転車を持っているのですが、輪行バッグに入れたままでずっと使っていませんでした。 当初は、子供とキャンプや遊びに行くときに持って行くと行動範囲が広がり楽しいかなと思って買ったのですが、しばらくして子供たちが成長し一緒に遊ぶ時間が減ってしまい、ずっと使わずにそのままになっていました。  たまには自転車をバッグから出してメンテナンスしなくちゃいけないと思い、点検することにしました。 自転車自体は屋内で保管しているため、少々埃を被っていたものの、錆や汚れの付着はなく綺麗な状態でした。変速機やブレーキも特に問題ありませんでした。唯一、タイヤの空気が抜けてべこべこしていたので、手動ポンプで空気を入れて点検終了です。 今回は実際に道路を走っていませんが、たぶん大丈夫だと思います。天気が良ければ、次の休日にこの自転車で周辺を走ってみようと思います。 せっかくの折りたたみなので、気が向いた時に、私一人でも自転車を車に積んでどこかでサイクリングしようかなと思っています。  |
||
【PR】
|
| 水槽 | ||
| 2025/3/7 | ||
|
先週はとても暖かく、日曜日は5月を思わせるほどでした。 そこで久しぶりにクマノミ水槽の掃除をすることにしました。掃除をする間、クマノミは別のバケツに移しておくので、なるべく水温低下の影響を受けないようにしたいからです。 水槽内のコケ取りと海水の2/3を入れ替え、気泡の出が悪くなったプロティンスキマーも清掃しました。 綺麗になった水槽にクマノミを戻すと、なんとなく嬉しそうにしている気がしました。我が家のクマノミは今年の9月で18年目を迎えます。熱帯魚屋さんで購入した時は1.5cmぐらいだったので、おそらく生後半年から1年くらい経っているのではないかと思います。なので、推定18歳か19歳ですね。 水槽はもう1つあり、子供が釣ったカエルウオを飼育していました。そのカエルウオですが、3ヶ月ほど前に死亡していました。岩陰に隠れていることが多いので気付かなかったのですが、何日も出てこないことから分かりました。残念でしたが、それでも7年間生きていたので寿命だったのだと思います。Webで調べてみると、カエルウオの寿命は3年から5年程と記載されていたので、特別なことをしていないけれど、長生きしてくれてありがとうと言う気持ちです。 その後の水槽は生体はいないのですが水を循環させています。水が減ってくると足し、いわゆる加湿器的な役割になっていますね。 この春にはポンプを停め、水を抜き、ろ材を取出してメンテナンスしようと思っています。使用しているポンプはレイシー(REI-SEA)の縦型ポンプで、もう25年間使っています。一度、異音がしたのでグリス注入などのメンテナンスをしたことがあるのですが、それ以外に不具合があった記憶はなく、とても丈夫で信頼性の高い製品だと感じています。さすが国産メーカーですね。まだまだ使えます。 今後のことはまだ何も考えていませんが、水槽をメンテした後に、また何か生物を飼育したいですね。  |
||
【PR】
|
| PCでお絵描き |
| 2025/2/28 |
|
前回の記事で、シジュウカラが単独で来ていると記しましたが、先の土曜日にツガイで来ている姿を見ました。 観察したところ、どうやら以前から来ていたツガイのようです。給仕箱からヒマワリの種を銜えて、お決まりの場所で食べていること、単独で来ている個体は違う場所で食べていたことからそう思いました。食べる場所はどこでも良いように思えるのですが、個体ごとに気に入った場所があるようです。 いつものツガイが帰ってきたと思うと安心しました。これで、もしかしたら今年も巣箱で子育てする姿が見られるかもしれませんね。 さて、今回の記事の題は「PCでお絵描き」です。 何度か記事にしていますが、私は趣味としてフリーソフトのGIMPとペンタブレットを使ってPCで絵本などを描いています。 今も次の作品用に描いているのですが、描くのに夢中になってしまい、気付いたら作品に合わない絵になってしまうことが時々あります。そのような場合でも、元の画像を保存していれば作業を戻すことが出来るので、デジタル作画は便利ですね。(保存を忘れて涙目になることもありますが…) つい先週もそのようなことがありました。シママングースの絵を描いていたのですが、描き込みすぎて写実的になってしまい、他の絵とのバランスから作業を一からやり直しました。 それでも、せっかく描いた絵のデータを削除するのは忍びないので、この場に掲載することにしました。手描きですが、GIMPを使い始めて1年半の素人でも、結構描けるものですね。基本的に、普通に紙に絵を描いたり色を付けたりするのとそれほど変わらないと思います。 外出先で気軽にスケッチとはいかないですが、PCでお絵描きもなかなか楽しいです。具材などの費用が掛からないのも助かりますね。 ※絵は作業を止めた時点のものなので、未完成のままです  |
| 【PR】 |
| 冬の庭先 |
| 2025/2/21 |
|
この冬も庭にある鳥用の給仕箱にひまわりの種や雑穀を入れ、小皿には切ったミカンの実を入れています。 やってくる鳥は、シジュウカラ、メジロ、ヒヨドリ、キジバトと言ったいつも見慣れた鳥たちです。 しかし、シジュウカラは去年と一昨年に庭の巣箱で子育てしたツガイは来ておらず、他の個体が1羽で来ています。今年も子育てが見られるか楽しみにしていたのですが、難しいかもしれません。 来ている個体は体が大きいので、たぶんオスだと思いますが、今後パートナーを見つけてやってくることもあるかもしれないので、それを待っていようと思います。  ミカンの実は、ヒヨドリが入れないように自転車カゴを逆さまにした中に皿に入れて置いてます。以前はヒヨドリも食べられるようにしていたのですが、ミカンの皮を摘んで持って行ってしまい、近隣に落ちていることがあったのでそうしました。自分の家の敷地内であれば構わないのですが、他所にごみを置かれるのはダメですからね。自転車カゴの網目はメジロが通れる大きさがあるので、メジロは中に入って食べています。 時折ヒヨドリがやってきますが、カゴの中に入れないのが分かり、以前のように頻繁に来たり鳴いたりしていないですね。 キジバトは以前から周辺に住んでいて、よく我が家の玄関前の樹に留まっているのを見ます。近頃は給仕箱からエサが落ちているのか、庭の地面を突いている姿をよく見ます。私たちが危害を加えないことを分かっているのか、かなり近くに寄っても逃げ出さずにいます。こちらが気付かない内に近くまで来ていて、逆に驚かされることもあります(笑)。 庭に小さな菜園があるのですが、今は野菜を植えずに花の球根を植えています。昨秋にアリウムの球根を幾つか植えてみました。大きな球形の花を付けるギンガチュームを2つ植えているのですが、芽が出てだいぶ大きくなってきましたよ。 小型のアリウムも植えており、全て無事に開花してくれると嬉しいですね。 アリウムは極端な乾燥を嫌うので、冬の間は地面が乾燥し易く水やりが必要なのですが、ついつい忘れてしまいます。大きくなってきたので、今後気を付けなければならないですね。  |
【PR】 |
| ワッペン |
| 2025/2/7 |
|
昨年、友人からキャリー付きのリュックサックを頂いて使用したところ、とても便利だったことを記事にしました。(小旅行用バッグ 2024/8/2 参照) その後、ひと回り大きいキャリーリュックを購入しました。選ぶに際して、引いて運ぶことが多いと思い、リュックの色は汚れの目立ちにくい「黒」にしました。年末年始の家族旅行ではそれに荷物を詰め込んで行きましたが、やはりキャリーが付いていると便利ですね。 しかし、1点だけ気になることがありました。飛行機で荷物を預けた場合、到着してターンテーブルから荷物を取る時に、黒色のバッグが多いので分かりにくいと妻に言われたのです。実は私自身も黒を選ぶ際にそう思い、自分の荷物だと分かる目印を付ければ問題ないだろうと考えていたのですが、そのままにしていたのです。 そこで、何か目印を付けることにしました。 初め、リュックにキーホルダーやピンバッジを付けようかと思ったのですが、輸送時に他の荷物と接触して外れる恐れがあるので却下し、リュックの生地が布製なので、布製ワッペンを貼ることにしました。 ワッペンはアイロンで押さえて熱で簡単に貼りつけられるものがあります。安価なものでも種類が沢山あるので、選ぶのに時間が掛かりました。 海外旅行に持っていくことも考え、ミリタリーや国を表すような物、過激なデザインは除外しました。オジさんの持ち物なのでキャラクター関連も敬遠しました(スターウォーズは気になっていたのですが辞めました)。いくつか候補を選び、貼れる面積を考慮して、最終的に2枚を注文しました。 ワッペンが届き、さっそくキャリーリュックに貼り付けました。ちょっと失敗(アイロンの熱でリュックのロゴが一部溶けて色が薄くなってしまった)してしまいましたが、誰でも持っていそうなリュックから、私のリュックになったように思えます(笑)。 ※写真は昼と夜で撮ったので、色味が違って見えます。  余談ですが、ワッペンは補修にも使えますね。私が30年ほど前に買ったダウンジャケットがあるのですが、何かに引掛けて右肩袖が破れてしまっていました、その補修にワッペンを使ったのです。当時スターウォーズシリーズのエピソード7「フォースの覚醒(2015年)」が上映されていて、その関連でユザワヤ(手芸用品・生地・ホビー材料専門店)でストームトルーパーのワッペンを売っているのを見つけ、それを買って貼り付けました。もう10年前の話ですが、気に入ったワッペンを貼ると、古着もさらに愛着が増しますね。着る頻度は少なくなっていますが、ジャケットの品質がしっかりしているので今も現役です。   |
| 【PR】 |
| 柚子酒 |
| 2025/1/31 |
|
12月初めに友人から柚子(ゆず)をいただきました。庭に植えてある樹に沢山なったので、持ってきてくれたのです。 さっそく柚子酒を作ることにしました。レモン酒作りの経験から、柚子は皮を剥いてざく切りにした実と、少量の皮を入れることにしました。皮から苦味成分が出すぎないようにするためです。 ホワイトリカーに柚子を漬けてから、年末に皮だけを取りだし、約2ヶ月経つので味見をしたところ良さそうだったので実も取り出しました。できたお酒は黄色味を帯びて綺麗です。 取り出した実はいつものようにジャムにしました。種が多く入っているので、濾器を使って実を潰しながら種を取り除き、出来た溶液にグラニュー糖を加え、煮詰めれば完成です。なかなか美味しく出来ましたよ。 柚子酒はほんのりと柚子の香りがして、口に含むと少し苦みを感じる甘すぎない甘味で丁度良いバランスのものになりました。もう1ヶ月ほど熟成させようと思います。  前に作っていたレモン酒ですが、3ヶ月経ち飲み頃になりました。これも美味しくできましたよ。レモンの風味と甘さ、程よい苦味が気に入っています。そのまま飲んでも良し、ソーダで割っても良し、ウォッカに混ぜてカクテルにして飲んでもなかなか良いですね。それから、お湯を入れてホットレモン酒にするとすごく美味しかったです。寒い季節にはぴったりですよ。ただ飲みやすいので飲みすぎには注意ですね(笑)。 これまでに作った桑の実酒、レモン酒、柚子酒を洗って取って置いたズブロッカの瓶に入れてみました。レモン酒はたまたまブランデーベースのリキュールを使ったので琥珀色になったのですが、3本並べると色の違いがあり見た目も綺麗でしょ? ズブロッカのバイソンの絵も気に入っています(笑)。  |
【PR】 |
| 長崎 |
| 2025/1/24 |
|
高台にあるホテルから見える長崎の夜景は、中心街に輝く光の集積を漆黒の長崎港の海と稲佐岳のシルエットが囲み、稲佐岳の頂上付近には柔らかに光る三日月が浮かんでいました。 1945年8月9日。この地に原子爆弾が投下されました。今年は被爆から丁度80年の年になるのですね。 長崎には小学生の頃に修学旅行で来ました。その時は、平和公園、グラバー邸、浦上天主堂、大浦天主堂を訪ねたのですが、記憶はなんとなくしか残っていません。原爆資料館に行った覚えがないのは、たぶん児童に与える影響を配慮して学校側が旅程に入れなかったのだろうと思います。それでも平和記念像の大きさや、天主堂の厳かな雰囲気は覚えています。 その長崎に家族で訪れました。レンタカーを借りて、初めに訪ねたのは平和公園です。今回の旅は全て妻が計画したのですが、教育的な意味も含めて、子供たちに戦争や原爆の事実に触れさせたいと思ったのだろうと思います。丁度、昨年の12月に「日本原水爆被害者団体協議会」がノーベル賞を授与されたのもあって、良いタイミングだったのかもしれません。  平和公園に着くと大勢の中国人観光客が平和記念像の前で写真を撮っていました。旗を持ったガイドに引き連れられて移動している姿を見て、何だか随分遠い昔の光景のようにも見えました。 平和記念像は小学生の頃に見たのと変わりなく、大きく尊厳を保っていました。右腕を上げて人差し指で空を指し、左腕を水平に伸ばした印象的なポーズです。「右手は原爆を示し、左手は平和を意味している。」と修学旅行の時にガイドさんから聞いた言葉は今も覚えています。記念像の両側には「折鶴の塔」と呼ばれる小さな塔があり、その中に市内の小学生が折った折鶴(千羽鶴)が沢山掛けられていました。因みに折鶴は千羽鶴にして、直接この塔に掛けても良いそうです。 記念像にお祈りを捧げた後、原爆資料館に行くことにしました。公園の中心の道を歩いていくと「平和の鐘」や各国から寄贈されたいくつかの像があり、その先には「平和の泉」がありました。この泉は、原爆で焼かれ水を求めながら亡くなった犠牲者の冥福を祈りつくられたものです。そのような背景を知ることはとても重要なことだと思います。 平和公園の先には「原爆落下中心地」がありました。広場になっていて、大きな黒い碑が立っていました。そして、崩れかけたレンガ作りの塔のような構造物があったのですが、それは崩れ落ちた浦上天主堂の南側遺壁の一部が移築されたものだそうです。 広場の先に長い階段があり、そこを登っていくと原爆資料館に着きました。受付ホールで入館手続きをし、らせん状のスロープを下りていくと入口があります。このスロープには年代が記されていて、過去に向けて下りていることを意味していました。 入口を入ってすぐ、「壊れた壁掛け時計」が展示されていました。外枠が壊れ、針は原爆が落ちた時間を指したまま止まっていました。館内には原爆の爆発の大きさや爆弾の仕組み、被害を物語る様々な物証、原爆が投下される経緯や、復興の歴史などが紹介されていました。 被害の物証は、破壊された建造物の一部や高温で溶けた瓶、女子学生が持っていた炭化した米の入ったお弁当箱など、とても多くの物が展示されていました。そして、投下後に生き残った人々の苦痛や悲しみを彷彿させる物品や手紙などもありました。それらを見ていると、とても心が苦しくなってくるのを感じました。しかし、実際に起こったことであり、目を逸らしてはいけないと自問しながらひとつひとつ見ていきました。 その先は自然光が入る明るいフロアーになり、各国の核兵器の保有状況などの説明がありました。そのエリアにはガラスケースに入れられた金色に輝くノーベル賞のメダルが慎まやかに展示されていました。特にアピールすることもなく置かれており、それにとても心を打たれました。メダルも女学生の弁当箱も、等しく価値のあるものと感じられたからです。 世界中の人々がここ(長崎)で起こった事実を知り、感じて欲しいと心から思います。 窓の向こうには長崎の美しい夜景が広がっていました。しかし私の気持ちに高揚感はなく、輝く光の一つ一つの基に、ここで亡くなった方々の魂があるように思え、静かで哀しさを伴った複雑な感情が心を包んでいました。  |
| 【PR】 |
| ハウステンボス |
| 2025/1/17 |
|
長崎県佐世保市にあるハウステンボスに初めて行きました。 中世のヨーロッパの街並みをイメージしたテーマパークの他に、パークの外にホテルや温泉施設もありました。かなり広く、敷地内を定期運行しているバスでホテルや温泉施設に行けます。勿論徒歩でも行けますがそれなりに時間が掛かります。私は温泉に行ってみたかったのですが、バスで行くのが面倒臭くなって結局行きませんでした。 パークは湾沿いに広がり、園内に運河が通っていました。風車もあって、なんとなくオランダのような雰囲気が感じられます。貰った園内マップを見てみると、湾奥のエリアはずばり「アムステルダムシティ」となっていました。そこには「マヘレの跳ね橋」のような橋もありました。各エリアには様々なアトラクションが用意されていて、閉園まで多くの人たちで賑わっていましたね。  私は並ぶのが好きではないので、日中は家族と別れて別行動することにしました。気ままに園内をぶらりお散歩です。子供と妻は目当てのアトラクションに行きました。アトラクションに並ぶ列は、どれを見ても40分~1時間ほど待つようでしたが、子供たちは5つか6つ体験して楽しかったようです。 私は各エリアを気ままにぶらぶら歩いていました。運河にはボートが定期運行していたのでそれに乗ってみたり、ベンチに座って花畑の中の風車を眺めたりしました。昼食には佐世保バーガーも食べましたよ。アトラクションなしでもそれなりに楽しめました。(初回だからこそと言うのもありますが…) ふと気付いたのは、レストランやお土産屋さんはあるのですが、園内にコンビニの類はありませんでした。街並み風ではありますが、テーマパークなので、人々の生活空間ではないのです。調べてみると、園の入口と出口付近の2ヶ所にコンビニがあるのが分かり、行ってみることにしました。ホテルの部屋でちょっとアルコールを嗜みたかったので、自分用に買っておきたかったのです。レストランでアルコールは飲めますが、やはり部屋でくつろいで飲みたいですからね(笑)。勿論、子供たちのお菓子も買いましたよ。 出口で手の甲にスタンプを押して出ると、入口から再入場できました。 夜のパークはライトアップされて本当に綺麗でした。クリスマスをテーマにしたプロジェクションマッピングも催されていました。家族で観覧車に乗ると(さすがに並びました)、街並みやガーデン一杯にイルミネーションの輝く光景が見られました。家族皆で観覧車に乗るのは本当に久しぶりで、それがとても嬉しかったですね。 閉園前には「ウィンターナイト花火」がありました。約10分ほどの花火のイベントなのですが、音楽に合わせて花火が打ち上げられ、とても感動しました。おそらく打ち上げの発火装置にプログラムが組まれて、最適なタイミングで花火に引火しているのだと思います。花火と音楽がシンクロした様がとても見事で、終わると自然に拍手していました。 家族と行ったハウステンボス、楽しめました。   |
| 【PR】 |
| 吉野ヶ里歴史公園 |
| 2025/1/10 |
|
佐賀県にある吉野ヶ里歴史公園に行ってきました。 実は、行くまではなんとなく遺跡があることを知っていたぐらいで大した知識はなく、特に期待感を持たずに行ったのですが、美しく整備された公園内に復元された古代の建物や発掘物の展示があり、とても興味深く素敵な公園でした。当公園は100ha以上の広さがあり、遺跡等を見学するだけでなく、散策するのにも良いですね。開けた草原を歩くのはとても気持ち良かったです。 訪れたのがお正月ということで、当公園で収穫された古代米で作った「おかず味噌」を一瓶貰えました。あたたかいご飯に乗せて食べても、練り物や焼き物に付けて食べても良さそうです。まだ蓋を開けていないのですが、ちょっとした記念日などで食べてみたいと思っています。楽しみですね。 私が味噌を貰って園内を散策している間、子供と妻は「勾玉づくり」の体験プログラムに参加していました。柔らかい高蝋石を砥石で磨いて作るのですが、綺麗に仕上げようと思うとそれなりに時間が掛かります。上の子は2時間磨いて1個作成しました。その間、下の子は2個作っていましたね。妻は1個作って、その後ずっと首に下げていました。  勾玉を作った後は、遺跡巡りをしました。竪穴式住居は他の場所で以前見たことがあったのですが、「南内郭」では、複数の住居や櫓(やぐら)が郭内に建てられいて、タイムスリップしたような感覚に捕らわれます。さらに驚いたのは「北内郭」の巨大な祭殿を中心とした建造物です。外からは、板壁が周囲を囲み内部が見られないようになっていて、入り口には真っ直ぐに入れないように鍵形に板壁が立てられていました。簡単に入れないような造りになっており、アニメや歴史映画で見たような感じがしました。内部に入ると、巨大な祭殿がでんと構えていて、威圧感さえ感じます。弥生時代にこのような建造物があったのかと圧倒されました。  「北墳丘墓」では発掘現場そのままの姿が展示されていました。墓の規模は大きく、また発掘現場の臨場感が感じられ、この展示は見応えがありました。この丘は人工的に作られた墓で14基の甕棺が見つかっているそうです。素焼きの甕(かめ)に亡骸を入れ蓋をして埋葬しており、中には青銅の剣などの副葬品が見つかっているものもありました。館内では埋葬の方法や発見された埋葬品の展示などもありました。  吉野ケ里遺跡を見て、自分の考えていた弥生時代の認識が大きく覆されました。私の弥生時代のイメージは学生の頃に教科書に載っていた「人々が農耕する画」の小さな村のイメージのままだったのです。弥生時代には既に高度な社会が形成されていたのだと深く認識を改めました。 「邪馬台国」の場所は九州説と近畿説がありますが、この遺跡を見せられると九州説もまんざら間違っていないように感じます。そして邪馬台国でないとしても、高度の文明が吉野ヶ里に繁栄していたことは間違いありませんね。 【参考】 〇吉野ヶ里歴史公園(公式HP) 吉野ケ里の歴史や、各遺跡の説明、園内マップなど詳細な情報が掲載されています。 |
| 【PR】 |
WALKABOUT